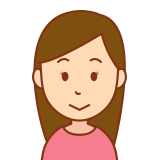
愛犬が腎臓病と診断されたり、腎臓の健康が気になるとき、食事の見直しはとても重要です。腎臓は老廃物を体外に排出する役割を担っており、腎機能が低下すると体にさまざまな不調を引き起こしてしまいます。
そこで注目したいのが、腎臓の負担を軽減できる療法食です。適切なフードを選ぶことで、腎臓の働きをサポートしながら、愛犬の生活の質を向上させることが期待できます。
本記事では、犬の腎臓ケアに最適なフードの選び方や、おすすめの療法食、与える際の注意点について詳しく解説します。大切な家族の一員である愛犬の健康を守るために、ぜひ参考にしてください。
犬の腎臓病とは?
犬の腎臓病は、腎臓の機能が低下することで体内の老廃物や余分な水分を排出できなくなる病気です。腎臓は、血液をろ過して尿を作る重要な臓器であり、その働きが低下すると体内に毒素が溜まり、さまざまな不調を引き起こします。
腎臓病は特に高齢の犬に多く見られますが、若い犬でも発症することがあります。慢性腎臓病として進行することが多く、気付いた時にはかなり進行しているケースも少なくありません。
犬の腎臓の役割
犬の腎臓は以下のような重要な役割を担っています。
1.老廃物の排出
血液をろ過して、老廃物や余分な塩分・水分を尿として排出します。
2.体内の水分や電解質の調整
体内の水分量やナトリウム、カリウムなどの電解質のバランスを保つ働きをしています。
3.ホルモンの分泌
赤血球を作るためのホルモンや、血圧を調整するホルモンを分泌します。
腎臓が正常に機能しなくなると、これらの働きが十分に行われなくなります。
犬の腎臓病の種類
腎臓病は大きく分けて急性腎不全と慢性腎臓病の2種類があります。
急性腎不全
突然腎臓の機能が低下する状態です。
中毒や感染症、脱水などが原因になることが多く、早急な治療が必要です。
適切な治療により回復する可能性があります。
急性腎不全の原因
急性腎不全は、腎臓の血流低下や腎臓への直接的なダメージが主な原因です。以下のような要因が考えられます。
1. 中毒
犬は誤って有害物質を摂取してしまうことがあります。
✅ ブドウやレーズン
✅ ユリ科の植物(特に猫にも有害)
✅ 人間用の薬(イブプロフェン、アセトアミノフェンなど)
✅ 殺鼠剤や農薬
✅ エチレングリコール(不凍液)
2. 感染症
✅ レプトスピラ症:細菌が腎臓に感染し、腎不全を引き起こします。
✅ 腎盂腎炎:尿路感染が腎臓まで進行した状態です。
3. 血流の低下
重度の脱水や出血、心不全などで腎臓への血流が減少すると、腎臓が正常に機能できなくなります。
4. 尿路閉塞
尿路結石や腫瘍により尿の排泄が妨げられ、腎臓に負担がかかります。
急性腎不全の症状
急性腎不全は、症状が急激に現れるのが特徴です。以下のような症状に注意しましょう。
✅ 突然の食欲不振
✅ 元気がなくなる
✅ 嘔吐や下痢
✅ おしっこが出ない、または量が極端に少ない
✅ 頻繁に水を飲む、または飲まなくなる
✅ 口臭が強くなる(アンモニア臭)
✅ 体が震える、痙攣する
✅ 意識がもうろうとする
このような症状が見られたら、すぐに動物病院を受診してください。
診断方法
動物病院では、以下のような検査を行い急性腎不全かどうかを診断します。
1.血液検査
BUN(尿素窒素)やクレアチニンの値を測定し、腎機能の状態を確認します。
2.尿検査
尿比重や尿中のタンパク質、血尿の有無を調べます。
3.超音波検査・レントゲン
腎臓の大きさや形の異常、尿路閉塞の有無を確認します。
4.血圧測定
腎臓病に伴う高血圧の有無を調べます。
治療方法
急性腎不全の治療は、原因の特定と症状の緩和を目的に行われます。
1. 点滴治療
体内の老廃物や毒素を排出するために、静脈点滴で水分と電解質を補います。
2. 薬物療法
✅ 感染症が原因の場合は抗生物質を使用します。
✅ 吐き気や痛みを和らげる薬を投与します。
3. 尿路閉塞の解除
尿路結石などによる閉塞がある場合は、カテーテルや手術で取り除きます。
4. 透析治療
重度の場合、血液透析や腹膜透析によって体内の毒素を除去します。
予後と回復
急性腎不全は、原因の特定と迅速な治療により回復の可能性があります。
しかし、重度の場合や治療が遅れた場合は、腎臓の機能が完全には回復せず、慢性腎臓病に移行することもあります。
治療後も定期的に腎機能の検査を行い、必要に応じて食事療法や薬物療法を継続します。
急性腎不全を防ぐためにできること
急性腎不全は、日常の注意で予防できるケースもあります。
1.有害物の管理
犬が届かない場所に薬や化学物質を保管しましょう。
2.誤食防止
ブドウやレーズン、ユリの花など犬に有害なものを与えないように注意します。
3.水分補給
十分な水分を摂取させることで腎臓への負担を軽減します。
4.定期的な健康診断
特にシニア犬は定期的に腎機能の検査を受けることをおすすめします。
慢性腎臓病(CKD)
慢性腎臓病(CKD:Chronic Kidney Disease)は、腎臓の機能が少しずつ低下し、長期間にわたって進行する病気です。
腎臓は血液をろ過して老廃物を尿として排出する重要な臓器ですが、腎臓の細胞は一度壊れてしまうと元に戻りません。
そのため、慢性腎臓病は完治が難しく、進行を遅らせるための治療や管理が必要になります。特にシニア犬に多く見られ、早期発見・適切なケアが愛犬の生活の質を維持する鍵となります。
犬の腎臓の役割
腎臓は以下のような働きを担っています。
✅ 老廃物の排出:血液中の老廃物を尿として排出します。
✅ 水分・電解質の調整:体内の水分量やナトリウム、カリウムのバランスを保ちます。
✅ ホルモンの分泌:赤血球を作るホルモンや血圧を調整するホルモンを分泌します。
慢性腎臓病が進行すると、これらの機能が低下し、体内に老廃物や余分な水分が蓄積してしまいます。
犬の慢性腎臓病の原因
慢性腎臓病の原因はさまざまですが、主に以下のようなものがあります。
✅ 加齢:加齢に伴い腎臓の機能が低下します。特に7歳以上のシニア犬は注意が必要です。
✅ 遺伝的要因:特定の犬種(キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル、シャーペイなど)は腎臓病のリスクが高いとされています。
✅ 腎臓の感染症:腎盂腎炎などの感染症が慢性化すると腎臓の機能が低下します。
✅ 結石や腫瘍:尿路結石や腎臓の腫瘍が腎機能を阻害することがあります。
✅ 高血圧:腎臓の血管に負担をかけることで腎不全を引き起こします。
犬の慢性腎臓病の症状
慢性腎臓病は初期には目立った症状が出にくいため、早期発見が難しい病気です。
病気が進行すると以下のような症状が現れます。
✅ 水をたくさん飲む・尿の量が増える
✅ 食欲がなくなる・体重が減る
✅ 元気がなくなる
✅ 毛艶が悪くなる
✅ 嘔吐や下痢
✅ 口臭が強くなる(アンモニア臭)
✅ 貧血によるふらつきや疲れやすさ
これらの症状が見られたら、早急に動物病院を受診しましょう。
犬の慢性腎臓病の診断方法
慢性腎臓病は以下の検査を通じて診断されます。
血液検査
BUN(尿素窒素)やクレアチニンの値が高いかどうかを調べます。
SDMA検査
初期の腎臓病の発見に役立つ新しい血液検査です。
尿検査
尿の濃縮具合やタンパク質の有無を確認します。
超音波検査・レントゲン
腎臓の形や大きさの異常を調べます。
犬の慢性腎臓病の治療方法
慢性腎臓病は完治が難しいため、進行を遅らせ、症状を緩和することが治療の目的となります。
1. 食事療法
腎臓病の進行を抑えるためには、療法食の利用が推奨されます。
・低タンパク質:腎臓に負担をかけにくい食事。
・低リン:リンの摂取を抑えて腎機能の低下を遅らせます。
・オメガ3脂肪酸:炎症を抑える効果が期待できます。
2. 薬物療法
・血圧を下げる薬:腎臓への負担を軽減します。
・リン吸着剤:リンの吸収を抑えます。
・造血剤:貧血が進行した場合、赤血球を増やす薬を使います。
3. 水分補給
・脱水を防ぐために水分をしっかり摂取させることが重要です。
・重度の場合は皮下点滴や静脈点滴を行うこともあります。
慢性腎臓病の進行度(ステージ分類)
国際的に用いられるIRIS(国際獣医腎臓病研究グループ)の基準では、慢性腎臓病はステージ1から4に分類されます。
・ステージ1:腎機能低下の兆候があるが症状は見られない。
・ステージ2:軽度の腎機能低下。水を多く飲むなどの軽い症状が見られる。
・ステージ3:中等度の腎機能低下。症状が目立ち始める。
・ステージ4:重度の腎機能低下。治療を行わないと命に関わる状態。
早期に発見し、ステージ1や2で適切な治療を始めることが重要です。
慢性腎臓病の予防方法
慢性腎臓病は完全に予防するのが難しいですが、次のような対策でリスクを下げられます。
・定期的な健康診断を受ける:シニア犬は年に2回の検査をおすすめします。
・水分をしっかり摂取させる:常に新鮮な水を用意しておきましょう。
・適切な食事管理:腎臓への負担を軽減するフードを与えます。
・肥満を防ぐ:肥満は腎臓に負担をかけるため、適正体重を維持しましょう。
犬の腎臓病についての資料
・慢性腎臓病は犬猫において多く見られる疾患
・生涯で慢性腎臓病に羅患する割合は猫で3頭中に1頭、犬で10頭中に1頭
・慢性腎臓病の羅患率は年齢に伴い上昇する
・慢性腎臓病の管理において確立した標準法として、ヒルズプリスクリプション・ダイエットk/d等の蛋白質、リン及びナトリウムを制限した腎療法食による栄養管理がある
・慢性腎臓病患者では、十分なカロリーと蛋白質を確実に摂取させることが治療の奏功と筋量の維持に重要
腎臓病の犬に食べさせるドッグフードの選び方

腎臓病の犬に食べさせるドッグフードの選び方
腎臓病の犬には、腎臓に負担をかけにくい専用のドッグフードを選ぶことが重要です。腎臓病は進行性の病気ですが、適切な食事管理を行うことで病気の進行を遅らせ、生活の質(QOL)を維持することができます。
ここでは、腎臓病の犬に適したドッグフードの選び方をわかりやすく解説します。
腎臓病の犬のためのフード選びのポイント
腎臓病の犬のフードを選ぶ際には、以下の点に注目しましょう。
1. 低たんぱく質
✅ たんぱく質は体に必要な栄養素ですが、腎臓が弱っている犬の場合、たんぱく質の代謝によって発生する老廃物(尿素窒素など)を排泄しきれなくなります。
✅ 低たんぱく質のフードを選ぶことで、腎臓の負担を軽減できます。
✅ ただし、極端にたんぱく質を制限すると筋肉量が減るため、犬の状態に合わせた調整が必要です。
2. 低リン
✅ リンは腎臓の機能低下に伴い体内に蓄積しやすくなります。
✅ リンの過剰摂取は腎臓病の進行を早めるため、低リン設計のフードを選びましょう。
✅ フードのパッケージに「低リン」や「リン制限」と記載があるものがおすすめです。
3. ナトリウム(塩分)の制限
✅ ナトリウム(塩分)の摂り過ぎは高血圧の原因となり、腎臓への負担を増大させます。
✅ 塩分控えめのフードを選ぶことで腎臓の負担を減らし、体内の水分バランスを保つことができます。
4. 高カロリー・良質な脂肪
✅ 腎臓病の犬は食欲不振になりがちです。
✅ 少量でもしっかりエネルギーを摂取できるように、高カロリーで消化の良いフードを選びましょう。
✅ 良質な脂肪(魚油や植物油)を含むフードが特におすすめです。
5. オメガ3脂肪酸の配合
✅ オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)は、腎臓の炎症を抑えたり、血流を改善したりする効果があります。
✅ サーモンオイルやフィッシュオイルが含まれているフードを選ぶと良いでしょう。
6. ビタミンB群の補給
✅ 腎臓病では尿中にビタミンB群が失われやすいため、不足しがちです。
✅ ビタミンB群が強化されたフードを選ぶことで、エネルギー代謝を助け、体調の維持に役立ちます。
腎臓病の犬に適したフードの種類
腎臓病の犬の状態や病期に応じて、適切なフードを選びましょう。
🥣 1. 療法食
獣医師が推奨する腎臓病用の療法食です。
腎臓への負担を軽減するように、たんぱく質・リン・塩分が調整されています。
例:
・ロイヤルカナン 腎臓サポート
・ヒルズ プリスクリプション・ダイエット k/d
・ピュリナ プロプラン ベテリナリーダイエット NF
🥩 2. 手作り食
・愛犬の状態に合わせた特別な手作り食も可能です。
・低たんぱく質・低リンで栄養バランスを考えながら調理します。
・ただし、栄養バランスの調整が難しいため、獣医師やペット栄養士と相談しながら作ることが重要です。
フード切り替え時の注意点
腎臓病用フードへの切り替えは、急に行わず徐々に進めることが大切です。
・1週間程度かけて、今までのフードに少しずつ混ぜながら切り替えていきます。
・食欲がない場合は、温めたり、水分を加えて柔らかくしたりすると食べやすくなります。
・また、食べムラがある場合でも無理に食べさせないようにしましょう。フードを変えることや投薬のタイミングを調整することで、食欲を取り戻せることがあります。
腎臓病の犬に食べさせるドッグフードの選び方まとめ
腎臓病の犬に適したフードを選ぶ際は、以下のポイントを押さえてください。
✅ 低たんぱく質・低リン・低塩分
✅ 高カロリー・良質な脂肪を含むもの
✅ オメガ3脂肪酸やビタミンB群を配合
✅ 獣医師推奨の療法食の利用
腎臓病の進行を遅らせるためには、食事管理と定期的な健康チェックが欠かせません。
愛犬の状態を見守りながら、少しでも快適な生活を送れるようサポートしてあげましょう。
腎臓病の犬に食べさせてはいけない食べ物
腎臓病の犬には、腎臓に負担をかける食べ物を避けることがとても大切です。特に以下の食品は、病気を悪化させる可能性があるため、注意が必要です。
1. 高リンの食品
腎臓病の犬は、リンの排出がうまくできなくなるため、血中のリン濃度が上がりやすくなります。リンが多すぎると腎臓の負担が増え、病気が進行する原因になります。
避けるべき食品:
✅ 内臓系の肉(レバー、ハツ、腎臓など)
✅ 乳製品(チーズ、ヨーグルト、牛乳など)
✅ 魚介類(しらす、煮干し、いくらなど)
✅ 豆類(大豆、納豆、豆腐など)
2. 高タンパクの食品
腎臓病の犬には、タンパク質の摂取量を調整する必要があります。タンパク質の代謝によって出る老廃物(尿素窒素など)は腎臓で処理されるため、摂りすぎると腎臓に負担がかかります。
避けるべき食品:
✅ 赤身肉(牛肉、豚肉、ラム肉など)
✅ 鶏肉(特にささみは高タンパク)
✅ 魚(まぐろ、かつお、鮭など)
※ ただし、適量の良質なタンパク質は必要なので、獣医師と相談しながら調整することが大切です。
3. 塩分の多い食品
腎臓病の犬は塩分(ナトリウム)の排出がうまくいかず、高血圧や浮腫(むくみ)を引き起こす可能性があります。そのため、塩分の多い食品は避けましょう。
✅ 避けるべき食品:
✅ 加工食品(ハム、ソーセージ、ベーコンなど)
✅ 塩漬け食品(梅干し、漬物、佃煮など)
✅ スナック菓子(ポテトチップス、クラッカーなど)
✅ 味付けされた料理(人間用の煮物やスープなど)
4. カリウムの多い食品(進行した腎不全の場合)
腎不全が進行すると、カリウムの排出が難しくなり、高カリウム血症になることがあります。高カリウム血症になると、心臓に悪影響を及ぼすため、カリウムが多い食品の摂取に注意が必要です。
避けるべき食品:
✅ バナナ
✅ アボカド
✅ ほうれん草
✅ さつまいも
✅ じゃがいも(特に皮付き)
※ ただし、腎臓病の初期段階ではカリウムが必要な場合もあるので、獣医師と相談しましょう。
5. 人間用の食べ物やおやつ
人間の食事には、犬にとって有害な成分が含まれていることが多いです。特に腎臓病の犬には、人間の食べ物は与えないようにしましょう。
避けるべき食品:
✅ チョコレートやカフェインを含む食品(腎臓だけでなく神経にも悪影響)
✅ ネギ類(玉ねぎ、長ねぎ、にんにく)(貧血を引き起こす可能性)
✅ ぶどう・レーズン(腎不全を引き起こす危険性)
✅ アルコール類(少量でも危険)
手作り食で腎臓をサポートする方法
腎臓病の犬に手作り食を与えることで、病状に合わせた食事管理ができ、より負担の少ない栄養バランスを取ることが可能になります。ただし、腎臓病の進行度によって必要な栄養バランスが異なるため、獣医師と相談しながら進めることが大切です。
1. 腎臓病の犬の手作り食で大切なポイント
① リンを制限する
腎臓病の犬はリンの排出が難しくなり、過剰なリンは病気を悪化させる原因になります。そのため、リンを控えめにすることが重要です。
✅ リンが少ない食材(おすすめ)
・白米
・さつまいも
・キャベツ
・かぼちゃ
・りんご
🚫 リンが多い食材(避けるべき)
・レバー(肝臓)、腎臓、ハツなどの内臓肉
・乳製品(チーズ、ヨーグルト、牛乳)
・魚介類(しらす、いくら、煮干し)
・大豆製品(豆腐、納豆、味噌)
💡 ポイント
・肉を茹でることでリンを減らせる(ゆで汁は捨てる)
・リン吸着剤(獣医師から処方されることがある)を併用すると効果的
② タンパク質の量を調整する
腎臓病の犬はタンパク質の摂取量を調整する必要があります。タンパク質の代謝による老廃物が腎臓に負担をかけるため、適量に抑えることが大切です。
✅ 良質なタンパク質を少量(おすすめ)
・鶏むね肉(皮なし)
・白身魚(タラ、ヒラメ)
・卵白(卵黄はリンが多いため控えめに)
🚫 高タンパクな食材(避けるべき)
・赤身肉(牛肉、豚肉)
・鶏ささみ(低脂肪だがタンパク質が多すぎる)
・魚の血合い部分(まぐろ、かつお)
💡 ポイント
・腎臓病の進行度に応じてタンパク質量を調整(獣医師と相談)
・植物性タンパク質より動物性タンパク質の方が消化しやすい
③ 塩分(ナトリウム)を控える
腎臓が悪くなると塩分の排出がうまくいかず、高血圧や浮腫(むくみ)を引き起こします。そのため、できるだけ塩分を控えた食事を作ることが重要です。
✅ 塩分が少ない食材(おすすめ)
・無塩の鶏肉・白身魚
・野菜(キャベツ、にんじん、かぼちゃ)
🚫 塩分が多い食材(避けるべき)
・人間の食事(味噌汁、煮物、スープなど)
・塩漬け食品(ハム、ベーコン、ちくわ、かまぼこ)
・スナック菓子(ポテトチップス、クラッカー)
💡 ポイント
・犬の食事には一切味付けをしない(出汁やスープも無塩にする)
④ カリウムの調整(進行した腎不全の場合)
腎臓病が進行すると、カリウムの排出が難しくなり、**高カリウム血症(不整脈などの原因)**になることがあります。
✅ カリウムを抑えたい場合(進行期)
・茹でた野菜(カリウムは水に溶けやすい)
・白米
🚫 カリウムが多い食材(注意が必要)
・バナナ、アボカド
・ほうれん草、さつまいも、じゃがいも
💡 ポイント
・野菜は一度茹でてカリウムを減らしてから与える
⑤ エネルギーをしっかり確保する
腎臓病の犬は食欲が落ちることがあるため、少量でしっかりエネルギーを摂取できる食事が理想です。
✅ エネルギー源としておすすめ
・ごはん(白米)
・さつまいも
・かぼちゃ
・良質な油(オリーブオイル、MCTオイル)
🚫 避けるべき油脂
・バター
・ラード
・揚げ物
💡 ポイント
少量の油を加えてエネルギー補給(特に食欲が落ちているとき)
2. 腎臓病の犬のための簡単レシピ
やさしい鶏と野菜のおじや
🔹 材料(1食分)
・鶏むね肉(皮なし)…50g
・白米 …1/2カップ
・かぼちゃ …20g
・キャベツ …20g
・水 …300ml
・オリーブオイル …小さじ1
🔹 作り方
1.鶏むね肉を一度茹でてリンを減らし、食べやすくほぐす。
2.かぼちゃとキャベツを細かく切る。
3.鍋に水を入れ、白米・野菜・鶏肉を加えて煮る。
4.野菜が柔らかくなったら火を止め、最後にオリーブオイルを加える。
5.粗熱をとってから犬に与える。
💡 ポイント
・野菜はよく煮込んで消化しやすくする。
・お米を主食にし、適量のタンパク質を加える。
・鶏肉を茹でることでリンの量を減らす。
3. 手作り食を与える際の注意点
✅ 必ず獣医師と相談しながら進める
✅ 栄養バランスが偏らないようにする(不足しやすいビタミン・ミネラルを補う)
✅ 食べない場合は無理をせず、療法食やサプリも検討する
腎臓病の犬の食べ物についてのQ&A
Q. 腎臓病の犬には市販のドッグフードと手作り食、どっちがいいの?
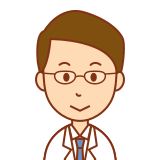
A: 療法食(市販の腎臓ケアフード)がおすすめ!
療法食は、腎臓病の犬に適した栄養バランスで作られているため、基本的には獣医師が推奨する療法食を与えるのが安心です。
✅ 手作り食が向いている場合:
・療法食を食べてくれない
・アレルギーなどの理由で市販フードが合わない
・獣医師と相談しながら、バランスを取れる場合
Q. 腎臓病の犬が食べてくれません…どうすればいい?
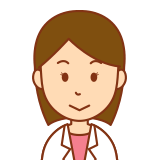
A: 腎臓病の犬は食欲が落ちることがあるため、工夫が必要です。
✅ 食欲アップの工夫
・フードを温める(香りが立ち、食いつきが良くなる)
・ふやかして柔らかくする(消化しやすくなる)
・少しだけオリーブオイルやMCTオイルを加える(風味とカロリーUP)
・いつもと違う器を使ってみる(気分を変える)
⚠ 無理に食べさせない
食べたくないときに無理に食べさせると、食べるのを嫌がる原因になります。食べない日が続く場合は、獣医師に相談しましょう。
Q. 腎臓病の犬におやつをあげてもいい?
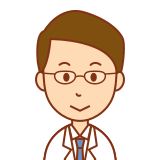
A: 基本的には、腎臓病用のおやつか、リンや塩分の少ない食材を使ったものが良いです。
✅ おすすめのおやつ
・茹でたかぼちゃ
・りんご(少量)
・腎臓病用の低リンおやつ(市販品)
🚫 避けるべきおやつ
・ジャーキー(リン・塩分が高い)
・乳製品(チーズ、ヨーグルト)
・人間用のクッキーやパン
💡 ポイント: 「少量ならOK」と言われることもありますが、できるだけ療法食を優先し、おやつは控えめにしましょう。
Q. 腎臓病の犬に水をたくさん飲ませても大丈夫?
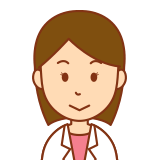
A: たくさん飲むのは問題なし!むしろ水分はしっかり取るべきです。
腎臓病の犬は、老廃物をうまく排出できなくなるため、水分補給が重要になります。
✅ 水分をとる工夫
・常に新鮮な水を用意する
・ウェットフードを活用する(ドライより水分が多い)
・ぬるま湯を少しフードにかける
⚠ ただし異常に水を飲む場合は要注意!
急に水を大量に飲むようになったら、病気が進行している可能性があるため、獣医師に相談しましょう。
まとめ
腎臓病の犬の食事では、「低リン・低塩分・適度なタンパク質」を基本とし、腎臓への負担を軽減することが大切です。特に、リンの摂取を抑えるために肉や魚は茹でる、塩分を含む加工食品は避ける、進行度に応じてカリウムの量を調整するなどの工夫が必要です。
また、食欲が落ちやすいため、フードを温める、オリーブオイルを加える、ふやかすなどの方法で食べやすくするとよいでしょう。療法食が基本ですが、食べない場合は獣医師と相談しながら手作り食を取り入れることも選択肢の一つです。
腎臓病の進行を遅らせ、愛犬が少しでも快適に過ごせるよう、日々の食事管理を工夫しながらサポートしていきましょう。
※出典


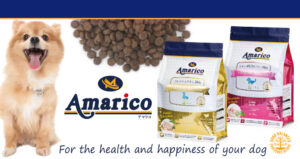



コメント