愛犬がてんかんと診断されたとき、「日常でできることはないだろうか」と感じる飼い主さんは少なくありません。
てんかんそのものを食事だけで治すことはできませんが、栄養バランスや原材料の選び方によって、発作のリスク要因や体調の安定をサポートできる可能性があります。
この記事では、獣医療的な診断や治療には触れず、あくまで日常生活での「食事の工夫」という視点から、ドッグフード選びのポイントをわかりやすくお伝えします。
犬のてんかんとは?
犬のてんかんとは、脳の神経が一時的に異常な電気信号を発することで、けいれんや意識の変化などの「発作」が起こる病気です。
人間のてんかんと同じように、発作は突然やってきます。
数秒で終わることもあれば、数分続くこともあり、その間は愛犬も飼い主さんもとても不安になる時間です。
てんかんには大きく分けて2つのタイプがあります。
1つは「特発性てんかん」と呼ばれ、明らかな病気やケガの原因が見つからないタイプ。
多くは1〜5歳の若い頃に発症します。
もう1つは「症候性てんかん」で、脳腫瘍や炎症、外傷など、脳に何らかの異常があって起こるタイプです。
発作の出方は犬によってさまざまです。
全身がガタガタ震えるような全般発作もあれば、体の一部だけがピクピク動く部分発作もあります。
中には、一瞬ぼーっとしたり、ふらついたりする軽い症状だけのこともあります。
てんかんは命に直結する病気ではありませんが、発作のたびに体力を消耗し、生活の質にも影響します。
大切なのは「てんかんとうまく付き合う」こと。
発作のパターンやきっかけを知り、日常生活や食事を含めてサポートしていくことが、愛犬の安心につながります。
犬猫のてんかんってどんな病気?
https://www.jstage.jst.go.jp/article/manms/18/4/18_354/_pdf
引用元:犬猫のてんかん
長谷川大輔 著
こちらの論文を飼い主さん向けにやさしく解説いたします。
🐾 犬猫のてんかんってどんな病気?
てんかんは、脳の神経が一時的に「電気の嵐」を起こすことで、体がけいれんしたり、意識が飛んだりする病気です。
人だけでなく、犬や猫にも起こります。
・犬では100匹に1匹くらい(犬種によってはもっと多い)
・猫ではもっと少なく、1000匹に4〜5匹程度
・発作は数秒〜数分で治まることが多いですが、繰り返すことがあります。
🐕🐈 どんなタイプがあるの?
てんかんには大きく分けて3つのタイプがあります。
▼遺伝性てんかん
…生まれつきの体質で起こる。特定の犬種で多いことも。
▼構造的てんかん
…脳のケガや腫瘍、炎症などが原因。
▼特発性(原因不明)てんかん
…検査してもはっきり原因が見つからないタイプ。
🕵️♀️ どうやって診断するの?
診断のカギは、発作の様子を正確に伝えることです。
獣医さんは「現場」を見られないので、動画がとても役立ちます。
さらに、血液検査やMRIなどで他の病気を除外します。
ただしMRIは麻酔が必要で、動物病院によってはできないこともあります。
💊 治療はどうするの?
基本は抗てんかん薬で発作を減らすことです。
発作を完全になくすのが理想ですが、現実的には
「生活に支障がないレベルまで減らす」ことを目指します。
投薬は毎日、同じ時間に
・勝手にやめると危険(発作が悪化することも)
・新しい方法としては、手術や食事療法(MCTオイル入りフード)、CBDオイルの研究も進んでいます。
📈 予後(よご)=その後の見通し
・犬では7割くらいが薬でコントロール可能
・平均寿命は、てんかんがあっても普通の犬とほぼ同じ
・猫も多くが薬で安定して、長生きできる
🐶🐱 飼い主さんができること
・発作時は慌てず安全を確保(ぶつかりそうな物をどける)
・発作の動画を撮って獣医さんに見せる
・薬は忘れず毎日同じ時間にあげる
・定期的に血液検査をして副作用をチェック
💡まとめ
てんかんは怖く感じるかもしれませんが、正しい診断と治療で、
ほとんどの犬猫が元気に暮らせます。
「動画」と「お薬の継続」が、飼い主さんからの一番のサポートです。
| 分類 | 詳細 |
|---|---|
| 特発性(Idiopathic) | 1.遺伝性(genetic)-原因遺伝子が同定されているか、家系図解析により遺伝性が明確なもの |
| 2.おそらく遺伝性(suspected genetic)-品種内発生率が2%以上、または家系図解析で家族性が強く疑われるもの | |
| 3.原因不明(unknown cause)-上記以外だが、特発性てんかんの診断基準を満たすもの | |
| 構造的(Structural) | 変性性(degenerative)/奇形性(anomalous)/腫瘍性(neoplastic)/炎症性・免疫性(inflammatory/immune)/外傷性(traumatic)/血管性(vascular) |
| 病因不明(Unknown etiology) | 特定できる原因がないもの |
| 反応性発作(非てんかん)(Reactive seizures) | 代謝性や中毒など、一時的な全身性の原因による発作 |
| 分類 | 下位分類 |
|---|---|
| 焦点性(focal) | 運動性(motor) |
| 自律神経性(autonomic) | |
| 行動性(behavioral) | |
| 全般性(generalized) | けいれん性(convulsive) |
| 強直間代性(tonic-clonic) | |
| 強直性(tonic) | |
| 間代性(clonic) | |
| ミオクロニー(myoclonic) | |
| 非けいれん性(non-convulsive) | 脱力(atonic) |
| 欠神(absence) | |
| 分類不能(unclassified) | – |
てんかんの基本的な症状と種類
犬のてんかんと聞くと「突然ひきつけを起こす病気」というイメージを持たれる方が多いと思います。
実際に、てんかん発作は脳の神経が一時的に異常な電気信号を出すことで起こります。
ただし、その現れ方は一つではなく、いくつかのタイプがあります。
もっともわかりやすいのは「全身けいれん型」と呼ばれる発作です。
急に意識を失ったように倒れ、手足をバタバタと動かしたり、口をカチカチさせたり、よだれを多く垂らすこともあります。
数分以内に治まることが多いですが、見ている飼い主さんにはとても衝撃的な姿に映るはずです。
一方で「部分発作」と呼ばれるタイプでは、全身ではなく体の一部だけに症状が出ます。
たとえば、顔の片側がピクピク動いたり、同じ方向にぐるぐる歩き回ったりするケースです。
この場合、意識が残っていることもあり「なんだかいつもと様子が違うな」と感じる程度で見過ごされることも少なくありません。
さらに、発作の前後には「前兆」や「後の症状」が出ることもあります。
発作の前には落ち着きがなくなったり、飼い主さんにしつこく甘えてきたりすることがあり、発作後にはしばらくボーッとしたり歩き方がふらついたりすることがあります。
てんかんは見え方や重さに個体差が大きいため、「よくある発作のパターン」を知っておくことが大切です。
そうすることで、いざというときに落ち着いて対処でき、動物病院で伝える際にも役立ちます。
発作に影響する可能性のある要因
犬のてんかん発作は、単に脳の異常だけでなく、いくつかの生活環境や体内バランスの変化によっても引き起こされることがあります。
発作の頻度や重さを少しでも減らすためには、どんな要因が関係しているのかを知っておくことが大切です。
ここでは、日常生活で注意したい主なポイントをご紹介します。
1. 食事と栄養バランス
食事内容は、犬の体内の神経伝達や代謝に大きく関わります。特に、
・過剰な糖質や添加物
・人工的な香料や着色料
・脂質のバランスの崩れ
これらは、血糖値の急上昇や神経系への刺激となり、発作を誘発することがあります。
特に、食後すぐに発作が起きるケースでは、ドッグフードの原材料や栄養バランスを見直すことが重要です。
2. 睡眠不足や生活リズムの乱れ
犬も人と同じように、生活リズムの乱れは脳にストレスを与えます。
・散歩や食事の時間が日によって大きく変わる
・夜遅くまで明るい環境で休めない
こうした状況が続くと、発作の引き金になることがあります。
できるだけ毎日のサイクルを整えて、安定した環境を作ってあげることが大切です。
3. 強いストレスや興奮
来客、騒音、引っ越しなど、環境の変化によるストレスも発作の原因になりやすいです。
また、大好きな飼い主さんとの遊びで興奮しすぎることもあります。
「遊んでいるときに急に発作が出る」というケースでは、遊びの強弱を調整したり、休憩をこまめに入れるなどの工夫が必要です。
4. 気温や湿度の変化
季節の変わり目や急な気温変化も、犬の体調に影響します。
特に、暑さや湿度の高さは体温調整を難しくし、発作のリスクを高めることがあります。
夏場は涼しい室内で過ごさせる、冬場は冷えすぎないよう注意するなど、環境管理も重要です。
5. 薬の影響や持病
てんかん治療薬の飲み忘れや、別の病気で使う薬が発作を誘発する場合もあります。
また、肝臓や腎臓の不調など、基礎疾患が影響するケースもあります。
かかりつけの獣医師とよく相談し、飲み合わせや体調変化には注意が必要です。
食事とてんかんの関係
犬のてんかんは、脳内の神経が異常に興奮して起こる発作ですが、その背景には「体内のバランスの乱れ」が関わっていることもあります。実は、毎日の食事内容や栄養バランスが、てんかん発作の頻度や重さに影響することがあるんです。ここでは、食事とてんかんの関係について、飼い主さんが知っておきたいポイントをわかりやすくお伝えします。
1. 血糖値の変動が発作に影響することも
犬の体は、血糖値の上下によって脳のエネルギー状態が変わります。血糖値が急激に上がったり下がったりすると、脳の神経が不安定になり、発作を誘発するケースがあります。
特に、炭水化物が多すぎるフードやおやつを与えていると、血糖値が乱れやすくなるため注意が必要です。
低GI(血糖値が上がりにくい)原材料を使ったドッグフードを選ぶのもひとつの方法です。
2. 脂質とタンパク質のバランスがカギ
最近の研究では、脂質をやや多めに、炭水化物を控えめにした「ケトジェニック(高脂質・低糖質)食」が、発作を抑える可能性があるといわれています。
ただし、犬の体質や年齢によっては脂質の摂りすぎが肝臓や膵臓に負担をかけることもあるので、自己判断ではなく獣医師と相談しながら取り入れることが大切です。
3. 添加物や原材料にも注意
市販のドッグフードには、香料・着色料・保存料などさまざまな添加物が使われている場合があります。
これらの中には、神経を刺激して発作を悪化させる可能性があるものもあります。
また、小麦やトウモロコシなど、犬によっては消化しにくい原材料が含まれていると、腸内環境が乱れて代謝にも影響が出ることがあります。
腸内環境の悪化は、てんかん発作のリスクを高める一因となることもあるため、できるだけ消化に優しく、添加物が少ないフードを選ぶのがおすすめです。
4. 栄養不足や偏りが神経系に影響
ビタミンB群、マグネシウム、タウリンなど、神経の働きをサポートする栄養素が不足すると、脳の興奮が抑えられにくくなることがあります。
例えば、ビタミンB6は神経伝達物質の生成に関わり、マグネシウムは神経の過剰な興奮を和らげる働きがあります。
栄養バランスが崩れていると、てんかんの症状が悪化する可能性があるため、総合栄養食を選ぶことが基本です。
5. 食事療法は獣医師と二人三脚で
てんかんの症状や原因は犬によって異なるため、「このフードが必ず効く」というものはありません。
大切なのは、愛犬の体質や持病、現在服用している薬との兼ね合いを考慮しながら、獣医師と相談して食事を調整することです。
場合によっては、療法食やサプリメントの導入が効果的なケースもあります。
栄養バランスが体調に与える影響
犬の体は、毎日の食事から摂る栄養でつくられています。
特にてんかんを抱える犬の場合、食事の栄養バランスが脳や神経の働きに影響し、発作の頻度や体調の安定にも関わってきます。
ここでは、栄養バランスが愛犬の体調にどのように影響するのか、飼い主さんが知っておきたいポイントをご紹介します。
1. タンパク質は「脳と神経の材料」
タンパク質は筋肉や皮膚だけでなく、脳や神経の働きを保つためにも欠かせません。
良質な動物性タンパク質が不足すると、神経伝達物質の生成に必要なアミノ酸が足りなくなり、脳の安定性が損なわれることがあります。
逆に、過剰なタンパク質は肝臓や腎臓に負担をかける場合もあるため、適切な量を意識することが大切です。
2. 脂質は「エネルギー源」として重要
犬は本来、脂質を効率よくエネルギーに変える体質を持っています。
特に、オメガ3脂肪酸(DHA・EPA)は神経細胞の保護や炎症の抑制に役立ち、てんかんを持つ犬にとっても有益とされています。
ただし、脂質の摂りすぎは肥満や膵炎などのリスクにつながるため、フードの成分表示をよく確認し、バランスの取れた量を与えることが大切です。
3. ビタミン・ミネラルが神経の安定に関わる
神経の興奮や脳の働きを落ち着かせるためには、ビタミンB群やマグネシウム、カルシウムなどのミネラルも欠かせません。
・ビタミンB6:神経伝達物質の生成に必要
・マグネシウム:神経の過剰な興奮を抑える
・カルシウム:筋肉や神経の正常な働きをサポート
これらの栄養が不足すると、脳の働きが不安定になり、発作の引き金になる可能性もあります。
4. 腸内環境と発作リスクの関係
近年の研究では、腸内環境と脳の健康には密接な関わりがあることが分かってきています。
腸内環境が乱れると、炎症物質や不要な代謝産物が増え、神経系に悪影響を与えることがあります。
添加物が少なく、消化しやすい原材料を使ったフードや、プロバイオティクスを含むフードを選ぶことで、腸内環境を整えやすくなります。
5. 偏った食事は体調を不安定にする
炭水化物や脂質が極端に多い、あるいは特定の栄養素だけを過剰に与えると、体内のバランスが崩れて体調不良を招くことがあります。
総合栄養食とされるフードを基本にしつつ、必要に応じてサプリメントで不足分を補うなど、「バランス重視」の食事管理がてんかん犬には特に大切です。
添加物や原材料に注意する理由
てんかんを持つ犬にとって、毎日の食事はただお腹を満たすだけでなく、体調を安定させるための大切なサポートになります。
その中でも特に気をつけたいのが、ドッグフードに含まれる 「添加物」 と 「原材料」 です。
これらは犬の体質や神経系に影響を与えることがあり、てんかん発作の頻度や重さに関係してくることもあります。
1. 合成添加物が神経に影響する可能性
市販のドッグフードの中には、保存性や見た目、風味を良くするために 人工的な香料・着色料・酸化防止剤 などが使われているものがあります。
特に、人工香料や化学的な酸化防止剤(BHA・BHT・エトキシキンなど)は、犬によっては神経系を刺激し、発作のリスクを高める可能性があると指摘されています。
もちろん、すべての犬に悪影響があるわけではありませんが、てんかんを持つ犬には避けたほうが安心です。
2. 消化しにくい原材料は腸内環境を乱す
小麦やトウモロコシ、大豆などの穀物や、副産物ミール(例:チキン副産物粉)を多く含むフードは、犬によっては消化に負担をかけることがあります。
腸内環境が乱れると、体内で炎症が起こりやすくなり、結果的に脳や神経への悪影響につながることもあります。特に、腸内環境と神経系の健康は密接に関係しているため、消化に優しい原材料 を選ぶことが大切です。
3. 不必要な添加物は「体内負担」に
ドッグフードの中には、見た目を良くするためだけの着色料や、嗜好性を高めるための強い香料が入っていることもあります。これらは犬にとって本来必要のない成分であり、肝臓や腎臓に負担をかける可能性があります。
てんかんを持つ犬は薬を服用していることも多いため、体内で薬と添加物の代謝が重なると、臓器への負担がさらに大きくなることがあります。
4. 原材料表示をしっかり確認する習慣を
フードを選ぶときは、パッケージの原材料表示を必ずチェックしましょう。
・「副産物」ではなく「チキン」「サーモン」など具体的な肉名が書かれているか
・「人工着色料」「合成保存料」などが含まれていないか
・「無添加」「グレインフリー」など愛犬の体質に合ったものか
こうした点を意識して選ぶことで、余計なリスクを減らすことができます。
5. 獣医師と相談して選ぶのが安心
てんかんの犬は、一見問題なさそうな成分でも反応してしまう場合があります。
自己判断だけでフードを決めるのではなく、かかりつけの獣医師に相談しながら進めると安心です。
特に療法食やサプリメントを併用する場合は、成分の重複にも注意が必要です。
ドッグフード選びのポイント
てんかんを持つ愛犬の食事は、発作のコントロールや体調管理にとってとても大切な要素です。
ドッグフードは毎日口にするものだからこそ、「どれを選ぶか」で体への負担や発作リスクが変わることもあります。
ここでは、てんかんを持つ犬のために意識したいフード選びのポイントを、わかりやすくご紹介します。
1. 添加物が少ないものを選ぶ
てんかん犬にとって、人工的な香料・着色料・保存料などの添加物はなるべく避けたいところです。
これらは嗜好性を高めたり見た目を良くするために使われますが、犬にとって必要な栄養ではありません。
特に、BHA・BHT・エトキシキンなどの合成酸化防止剤は、神経系に影響を与える可能性があると指摘されることもあります。できるだけ「無添加」や「自然由来の保存料」を使っているフードを選ぶと安心です。
2. 良質なタンパク質をしっかり摂れるか
犬にとってタンパク質は、筋肉や皮膚はもちろん、脳や神経の働きに欠かせない栄養素です。
おすすめは、「チキン」「サーモン」「ラム」など具体的な肉や魚を第一原料に使っているフードです。
「副産物ミール」や「動物性油脂」など、原材料が不明瞭なものは避けた方が安心です。
良質なタンパク質をしっかり摂ることで、神経伝達物質のバランスを保ち、体調を安定させるサポートにつながります。
3. 炭水化物の質と量に注目
てんかんを持つ犬の場合、血糖値の急な変動が発作のきっかけになることがあります。
そのため、炭水化物を多く含むフードよりも、低GI(血糖値が上がりにくい)原材料を使ったものがおすすめです。
例えば、白米や小麦よりも、サツマイモ・玄米・オートミールなど、消化が穏やかで栄養価の高い炭水化物を使ったフードが適しています。
4. オメガ3脂肪酸などの「神経サポート成分」
てんかん犬のドッグフード選びでは、神経の健康を助ける栄養素が含まれているかも重要です。
特に、オメガ3脂肪酸(DHA・EPA)は神経細胞を保護する働きがあるとされ、サーモンオイルや亜麻仁油などに多く含まれています。
また、ビタミンB群、マグネシウム、タウリンなども神経の安定に関わるため、バランスよく配合されたフードを選ぶとより安心です。
5. 消化しやすさも大切なポイント
腸内環境が乱れると、体内の炎症反応や神経への影響が出ることがあります。
犬によっては小麦や大豆などの穀物を消化しにくい場合があるため、グレインフリー(穀物不使用)フードや、消化に優しい原材料を使ったものを検討するのも一つの方法です。
また、プロバイオティクス(乳酸菌)や食物繊維が配合されたフードは、腸内環境を整えやすくおすすめです。
6. 獣医師と相談しながら選ぶ
てんかんは犬によって原因や症状が異なるため、「このフードが絶対にいい」という正解はありません。
発作の頻度や薬の服用状況、体質を踏まえて、かかりつけの獣医師と相談しながら最適なフードを選ぶことが大切です。療法食を提案される場合や、サプリメントとの併用が必要なケースもあります。
原材料表示の見方
てんかんを持つ愛犬のドッグフードを選ぶとき、パッケージの「原材料表示」はとても大切なチェックポイントです。
どんな原材料が使われているかによって、発作リスクや体調への影響が変わることもあります。
ただ、表示を見ても専門用語が多くてわかりづらいこともありますよね。
ここでは、原材料表示をチェックするときのポイントを、わかりやすく解説します。
1. 原材料は「多い順」に書かれている
原材料は、使用量が多い順に記載されています。
つまり、表示の最初に書かれている食材が、そのフードのメイン原料です。
てんかん犬の場合は、「チキン」「サーモン」「ラム」など具体的な動物性タンパク質が一番最初に書かれているフードがおすすめです。
逆に、トウモロコシや小麦などの炭水化物が先に来ている場合は、糖質過多になる可能性があるため注意が必要です。
2. 「副産物」や「あいまいな表現」に要注意
原材料名に「チキン副産物ミール」「動物性油脂」など、何の部位を使っているか不明確なものは避けたほうが安心です。
副産物自体が必ずしも悪いわけではありませんが、質の低い原料が含まれているケースもあります。
特にてんかんを持つ犬は、消化への負担や添加物の影響を受けやすいので、なるべく原材料が明確なフードを選ぶようにしましょう。
3. 添加物・保存料の種類をチェック
原材料表示には、香料・着色料・酸化防止剤などの添加物も記載されています。
特に注意したいのは、BHA・BHT・エトキシキンといった合成酸化防止剤です。
これらは長期的に摂取すると体内に負担をかける可能性があり、てんかん犬には避けたほうが無難です。
一方で、ビタミンE(ミックストコフェロール)やローズマリー抽出物など、自然由来の保存料を使っているフードは比較的安心です。
4. アレルギーになりやすい食材も確認
犬によっては、小麦・大豆・乳製品・トウモロコシなどが体質に合わない場合があります。
これらを摂取すると腸内環境が乱れ、結果的に神経系にも影響することがあります。
もしアレルギーや消化不良が気になる場合は、グレインフリー(穀物不使用)や、消化に優しいサツマイモ・豆類を使ったフードを検討してみると良いでしょう。
5. 「総合栄養食」かどうかを確認する
原材料だけでなく、パッケージに「総合栄養食」と記載されているかどうかも大切です。
総合栄養食とは、AAFCO(米国飼料検査官協会)やペットフード公正取引協議会の基準を満たし、犬に必要な栄養素をバランスよく含んでいるフードのことです。
おやつやトッピングだけでは必要な栄養が足りないため、まずは総合栄養食をベースに考えるのが安心です。
消化にやさしいフードの特徴
てんかんを持つ犬にとって、消化に負担の少ないフードを選ぶことはとても大切です。
消化不良を起こすと体内で炎症が起きたり、代謝に余計なエネルギーを使ってしまい、体調が不安定になりやすくなるからです。
ここでは、消化にやさしいフードを見分けるポイントをいくつかご紹介します。
まず大切なのは、原材料の質です。
鶏肉や魚などの動物性たんぱく質が新鮮で、過度に加工されていないものを使っているフードは消化しやすい傾向があります。
逆に、副産物や加工肉が多いフードは、胃腸に負担をかける場合があるので注意が必要です。
次に、炭水化物の種類もポイントです。
小麦やとうもろこしなどはアレルギーを引き起こすこともあり、消化に時間がかかる場合があります。
代わりに、玄米・さつまいも・かぼちゃなど、食物繊維を含みつつも消化吸収が穏やかな食材を使っているフードがおすすめです。
さらに、添加物や香料が少ないことも大切です。
人工的な着色料や保存料は、消化器官に負担をかけるだけでなく、体内の代謝を乱す可能性もあります。
最後に、粒の大きさや形状にも注目しましょう。
小型犬であれば小粒タイプの方が噛みやすく、胃腸への負担も軽くなります。
また、ふやかして与えられるタイプや、低温でじっくり加熱されたエアドライ製法のフードも消化にやさしい傾向があります。
てんかんを持つ犬は、体調のちょっとした変化が発作につながることもあります。
消化にやさしいフードを選ぶことで、体内のバランスが整いやすくなり、発作リスクの軽減にもつながります。
高脂肪・高糖質に偏らないバランス
てんかんをもつ犬の食事では、「高脂肪」「高糖質」に偏らないバランスがとても大切です。
脳の健康を守るにはエネルギー源となる栄養素は欠かせませんが、過剰な摂取はかえって発作のリスクを高めることもあるため注意が必要です。
まず脂肪についてですが、良質な脂肪は犬にとって重要なエネルギー源であり、細胞やホルモンの働きにも関わっています。
ただし、あまりに脂肪が多すぎると、体重増加だけでなく肝臓への負担も大きくなります。
特にてんかんの犬では、肝機能が弱ると薬の代謝に影響が出ることもあるため、原材料欄で「動物性油脂」「植物油」などの表記をチェックして、適量かどうかを意識することが大切です。
また、糖質のとりすぎにも注意が必要です。
犬は炭水化物をエネルギーに変えることができますが、血糖値が急激に上がると神経の興奮が強まり、発作のきっかけになる可能性もあります。
小麦やとうもろこしなど高GI(血糖値を上げやすい)原料が多いフードよりも、玄米やさつまいもなど、ゆっくりとエネルギーになる原料を使ったフードの方が安心です。
最終的には「タンパク質・脂質・糖質のバランス」がポイント。
高たんぱく・適度な脂質・低めの糖質を意識したレシピを選ぶことで、発作リスクの軽減につながるだけでなく、体重管理や内臓への負担軽減にも役立ちます。
日常でできる食事の工夫
てんかんを持つ愛犬にとって、日々の食事は症状の安定にもつながる大切な要素です。
特別な療法食を使う場合もありますが、普段のごはんの与え方や工夫次第で、体への負担を減らすことができます。
ここでは、毎日の食事で意識したいポイントをご紹介します。
1. 食事の時間をできるだけ一定にする
てんかんは生活リズムの乱れがきっかけで発作を誘発することがあります。
朝・晩のごはんの時間をできるだけ毎日同じにすることで、血糖値の急激な変動を避け、体内のバランスを保ちやすくなります。
2. 一度にたくさん与えすぎない
お腹いっぱい食べた後は消化にエネルギーが使われ、体に負担がかかります。
特にてんかんを持つ子は、消化のストレスが引き金になってしまうことも。
1日の量を2〜3回に分けて与える「分食」を意識すると、体への負担を和らげられます。
3. 間食は低脂肪・低糖質のものを選ぶ
おやつは愛犬との大切なコミュニケーションですが、高脂肪・高糖質なものは血糖値の急上昇や体重増加につながります。ササミ、ボイルした野菜、低脂肪のドッグトリーツなど、消化にやさしいものを選ぶと安心です。
4. 水分補給をしっかり意識する
てんかんの子は、発作時の筋肉の緊張などで体内の水分が失われやすくなります。
脱水は体調の悪化につながるため、常に新鮮なお水を用意してあげましょう。
食欲が落ちているときは、フードに少し水や無塩のスープをかけて与えるのもおすすめです。
5. 新しいフードは少しずつ慣らす
フードを切り替えるときは、急に変えるとお腹を壊す原因になります。
新しいフードを少しずつ混ぜ、1週間から10日ほどかけて徐々に切り替えるのが理想です。
腸内環境が安定しやすく、発作リスクも抑えられます。
与える量とタイミングの安定化
てんかんを持つ犬にとって、食事のリズムを安定させることはとても大切です。
なぜなら、急な血糖値の変動や空腹時のストレスが発作のきっかけになる場合があるからです。
まず意識したいのは「毎日同じ時間に、同じ量を与える」ということ。
人間でも生活リズムが乱れると体調に影響が出るように、犬も食事のペースが安定していると体が落ち着きやすくなります。
朝と夕方の1日2回に分けて与えるのが基本ですが、発作が心配な子はさらに小分けにして1日3回以上に調整することもあります。
また、与える量については「太らせない、痩せさせない」が鉄則です。
肥満は発作のリスクを高める要因になる一方、痩せすぎは体力を落としてしまいます。体重の変化をこまめにチェックしながら、その子に合った適量を続けることが大切です。
さらに注意したいのは、おやつや人の食べ物を不規則に与えること。
せっかく食事で整えたリズムが崩れてしまうので、与えるなら必ずルールを決めて、ドッグフードの量から調整するようにしましょう。
つまり「量」と「タイミング」を安定させることは、栄養面の管理だけでなく、犬の安心感にもつながります。
毎日の食事を同じリズムで続けることが、てんかんのある犬の生活をより穏やかに支えるポイントなのです。
水分補給の工夫
てんかんを持つ犬にとって、実は「水分の取り方」も大切なポイントです。
体の水分バランスが崩れると代謝に影響が出やすく、それが発作を誘発するきっかけになることもあるからです。
まず基本は、いつでも新鮮な水を飲める環境を整えること。
朝と夜の2回取り替えるのではなく、できればこまめにチェックして常にきれいな状態を保ってあげましょう。
特に夏場や暖房の効いた冬場は思っている以上に水分を失いやすいため、飲む量が減っていないか注意して見てあげる必要があります。
もし水だけではあまり飲まない子であれば、フードに工夫を加えるのもおすすめです。
ドライフードにぬるま湯をかけてふやかしたり、ウェットフードを取り入れることで自然に水分を摂取できます。また、鶏のゆで汁を薄めて水に混ぜるなど、風味を加えることで飲みやすくなる場合もあります。
ただし、塩分や糖分を含む人間用の飲み物やスープは絶対にNGです。
知らず知らずのうちに体に負担をかけ、てんかんだけでなく腎臓や心臓の病気につながる危険があります。
水分補給は、ただ「水を飲ませる」だけではなく、その子の生活スタイルや体調に合わせて工夫してあげることが大切です。
日々のちょっとした心配りが、発作を少しでも減らすサポートになり、安心して過ごせる時間を増やすことにつながります。
間食やおやつの注意点
てんかんを持つ犬にとって、間食やおやつの与え方には特に注意が必要です。
おやつは犬とのコミュニケーションやトレーニングに役立つ反面、与え方を間違えると血糖値の急な変動を招いたり、肥満につながり、結果として発作のリスクを高めてしまうことがあります。
まず大切なのは「与える量を管理する」ことです。
おやつはあくまで補助であり、主食のドッグフードに影響しない程度に抑えることが基本です。
目安としては1日の総カロリーの10%以内が望ましいとされています。与えすぎてしまうと、体重が増えて代謝や神経系に負担をかけることになるため注意しましょう。
また「内容」にも気をつけたいところです。
人間用のお菓子や味付けされた食べ物は、塩分や糖分、添加物が多く含まれており、てんかんを持つ犬には特に避けたいものです。
市販のおやつを選ぶ際は、できるだけシンプルな原材料のものや、低脂肪・低カロリーの製品を選ぶと安心です。さらに、手作りをする場合でも味付けは一切せず、茹でた野菜や少量のささみなど、素材そのままのものを意識すると良いでしょう。
そしてもうひとつ大切なのが「タイミング」です。
食事と食事の間に与えることで、空腹時間を長くしすぎない工夫になる場合もありますが、あまり不規則に与えると食事リズムが乱れてしまいます。
毎日の食事時間とバランスを考えながら、おやつも計画的に取り入れることが大切です。
「少しだけなら…」とつい甘やかしたくなる気持ちは飼い主として自然なことですが、てんかんを抱える犬にとってはその一口が体調に響くこともあります。
おやつは愛情を伝えるための手段のひとつですが、その子の健康を守ることこそが、何より大きな愛情表現になるのです。
食事管理とあわせて気をつけたい生活習慣
てんかんを持つ犬の健康を守るためには、食事の管理だけでなく、日常の生活習慣にも目を配ることが大切です。毎日のちょっとした過ごし方が、発作の起こりやすさや愛犬の安心感に大きく関わってきます。
まず意識したいのは「生活リズムの安定」です。不規則な生活や急な環境の変化は犬にとって大きなストレスになり、発作を誘発することがあります。
できるだけ決まった時間にご飯をあげたり、散歩や休む時間を一定にしてあげると、犬の心と体が落ち着きやすくなります。
次に「十分な休養」です。睡眠不足は人間と同じく神経に負担をかけ、てんかん発作のきっかけになることがあります。静かで安心できる寝場所を用意し、家族が騒がしい時間帯でもゆっくり休めるように工夫してあげましょう。
また「過度な興奮を避ける」ことも大切です。
激しい運動や大きな音、急な驚きなどは犬の神経を刺激し、発作を誘う要因になりかねません。
もちろん散歩や遊びは大切ですが、その子の体調に合わせて無理のない範囲で行うことがポイントです。
さらに「定期的な健康チェック」も欠かせません。
体重の変化や発作の頻度、食欲や水分摂取量など、日々の小さな変化を見逃さないように記録しておくと、動物病院での診察にも役立ちます。
食事管理とあわせてこうした生活習慣を整えることで、発作のリスクを少しでも減らし、愛犬が穏やかに過ごせる時間を増やすことができます。
大切なのは「特別なことをする」よりも「毎日の暮らしを安定させる」こと。飼い主さんのちょっとした心配りが、犬にとって大きな安心につながるのです。
発作の記録をつける
てんかんを持つ犬と暮らすうえで、とても役立つのが「発作の記録」を残すことです。
発作はいつ起こるか予測が難しく、病院に行く時にも「どんな発作が、どのくらいの頻度で起きているのか」を正しく伝えることが診断や治療の手がかりになります。
記録するときのポイントは、できるだけ具体的に残すことです。例えば、
・発作が起きた日時と時間帯
・発作の前に見られた様子(落ち着きがなくなる、震え、よだれなど)
・発作の持続時間
・体のどの部分に症状が出たか(全身か、一部の筋肉か)
・発作後の様子(ぐったりしている、ふらつく、普段通りに戻る など)
こうした情報をノートに書き留めるのも良いですし、最近はスマホのアプリやカレンダーを使って記録する飼い主さんも増えています。
発作中に余裕があれば動画を撮っておくのも、獣医師が症状を正確に把握する助けになります。
また、食事やおやつの内容、運動量、天候、生活の変化なども一緒にメモしておくと「発作のきっかけ」や「発作が出やすい条件」が見つかる場合があります。
例えば、夜更かしした翌日や急に暑くなった日に発作が起きやすい、などの傾向が見えてくることもあるのです。
記録は単なるメモではなく、愛犬の体調を守るための大切なデータです。
日々の積み重ねが、獣医師との連携をよりスムーズにし、治療の精度を高めてくれます。
発作に悩む愛犬と安心して向き合うために、ぜひ「記録する習慣」を取り入れてみてください。
ストレスを減らす環境づくり
てんかんを持つ犬にとって、日常の「ストレス」は発作を誘発する大きな要因のひとつです。
人間と同じように、犬も不安や緊張が続くと神経が過敏になり、体調に影響が出やすくなります。
そのため、食事管理とあわせて“安心して過ごせる環境づくり”を心がけることが大切です。
まず意識したいのは「静かで落ち着ける空間」を用意してあげることです。
大きな物音や急な来客、にぎやかな環境は犬にとって強い刺激になります。
ハウスやベッドなど、愛犬が安心できる自分だけの居場所を作り、そこでは家族もあまり構いすぎないようにすると良いでしょう。
また「生活リズムの安定」もストレスを減らすカギです。
ご飯や散歩、遊びの時間をできるだけ毎日同じにすることで、犬は先の予定を予測できるようになり、不安が少なくなります。特にてんかんを持つ犬には、規則正しい暮らしが安心感につながります。
さらに「無理のない刺激」が大切です。たとえば散歩は気分転換や運動として必要ですが、長時間歩かせたり、人混みや騒音の多い場所へ連れて行くのは控えた方が安心です。その子の体調や性格に合わせて、のんびり過ごせるコースを選ぶのが理想です。
そして何より、飼い主さん自身が落ち着いて接することも重要です。
飼い主の緊張や不安は犬に伝わりやすく、逆にリラックスした態度で接してあげることで犬も安心できます。
ストレスを減らす環境づくりは特別なことではなく、日々のちょっとした配慮の積み重ねです。
愛犬が「ここなら安心できる」と感じられる環境を整えることが、てんかんと向き合ううえで大きな支えになります。
まとめ
犬のてんかんと食事には、切っても切れない深い関わりがあります。
ドッグフードの選び方はもちろん、与える量やタイミング、水分補給、間食の管理など、日々の食事習慣を整えることが、発作のリスクを減らす大切なポイントになります。
さらに、生活リズムを安定させたり、十分な休養をとれる環境をつくることも欠かせません。
また、発作の記録を残して獣医師と共有したり、ストレスを減らすための安心できる空間を整えることも、愛犬の穏やかな毎日に直結します。大切なのは「特別なことをする」よりも「毎日を安定させる」こと。
その積み重ねが愛犬の健康を支え、飼い主にとっても安心につながります。
てんかんを持つ犬と向き合うのは簡単なことではありませんが、ちょっとした工夫や心配りで、愛犬はもっと快適に、そして穏やかに暮らしていけます。飼い主さんの手で整える日々の習慣こそが、愛犬にとって最大のサポートになるのです。


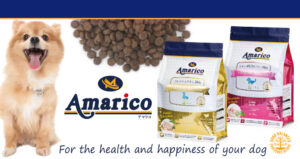
』の口コミ・わんちゃんの写真-120x68.jpg)
コメント