「血液検査で高脂血症と言われたけれど、どんなドッグフードを与えればいいの?」
そんな不安を抱える飼い主さんは少なくありません。高脂血症はすぐに症状が出るわけではありませんが、放っておくと膵炎や肝臓への負担などにつながることもあります。そこで今回は、犬の高脂血症の原因と、日常の食事でできるサポート方法についてお伝えします。
犬の高脂血症とは?
犬の高脂血症とは、血液の中に脂質(中性脂肪やコレステロール)が通常よりも多く含まれている状態を指します。簡単に言えば、血液が“油分過多”になっているイメージです。
本来、脂質は体を動かすエネルギー源として欠かせないものですが、必要以上に増えると血液がドロッとした状態になり、内臓や血管にじわじわと負担をかけていきます。
犬の場合、人間と違って「動脈硬化で心筋梗塞」というイメージはあまりありません。
ただし、油断は禁物です。
高脂血症をそのままにしておくと、膵炎や肝臓へのダメージなど、命に関わる病気を引き起こすきっかけになることがあります。
特に膵炎は急激に悪化することもあり、飼い主さんにとっても愛犬にとっても大きな負担になります。
また、高脂血症には「一時的に起こるもの」と「体質や病気が背景にあるもの」の2種類があります。
たとえば食後すぐに血中脂質が上がるのは自然な反応ですが、時間が経っても数値が下がらない場合や、空腹時でも数値が高い場合は注意が必要です。
見た目にはわかりにくく、症状もすぐには現れないことが多いため、「隠れ病気」と呼ばれることもあるのが高脂血症のやっかいなところ。
だからこそ、血液検査で指摘されたときには食事や生活習慣を見直すサインだと受け止めることが大切です。
血液中の脂質が多すぎる状態
犬の高脂血症は、血液の中に中性脂肪やコレステロールといった“油分”が必要以上に増えてしまった状態です。血液は本来サラサラと流れるのが理想ですが、脂質が多すぎるとドロッとした“油っぽい血液”になってしまいます。
この状態が長く続くと、血液をろ過したり、栄養を処理する肝臓や膵臓に負担がかかります。
特に膵臓は脂質に敏感で、急性膵炎を起こすリスクが高まるとされています。
犬の場合、人間のように動脈硬化から心筋梗塞…というパターンは少ないものの、内臓にじわじわダメージを与える点では同じです。
血液中の脂質は、食事の内容や量、体質、さらには他の病気の影響でも変動します。
そのため「数値が高い=必ず病気」というわけではありませんが、油断すると大きなトラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。
気づきにくい“隠れたサイン”
高脂血症のやっかいな点は、見た目ではほとんど気づけないことです。
多くの犬は、数値が高くても普段どおり元気に見えます。
そのため「血液検査で初めて分かった」というケースがほとんどです。
ただ、よく観察すると小さな変化が隠れていることもあります。例えば、
・食べていないのに体重が増える
・被毛にベタつきが出てきた
・すぐ疲れやすい
・便が柔らかい、下痢を繰り返す
といったサインが見られることがあります。
これらは一見「ちょっとした不調」に思えますが、血液中の脂質バランスが乱れている影響かもしれません。
つまり、高脂血症は“静かに進行する隠れたリスク”と言えます。
健康診断や血液検査で早めに気づければ、食事の見直しや生活習慣の工夫でコントロールできる病気でもあるのです。
犬が高脂血症になる主な原因
犬の高脂血症は、ひとつの理由だけで起こるわけではありません。
体質や年齢、生活習慣、さらには他の病気の影響など、いくつかの要因が重なって血液中の脂質が増えてしまいます。
主な原因を整理すると次のようになります。
遺伝や体質によるもの
特定の犬種や体質によって、脂質代謝がうまくいかない子がいます。
特にシェットランド・シープドッグやミニチュア・シュナウザーなどは高脂血症が起こりやすいと知られています。こうした場合、食事に気をつけても数値が下がりにくいことがあり、体質として「脂質をため込みやすい」傾向があると言えます。
食べすぎや高脂肪な食事
一番多いのは、やはり日常の食事です。カロリーや脂肪分が多いフード、あるいは人間の食べ物や脂っこいおやつを与えることで、血液中の脂質が増えてしまいます。
特に運動量が少ない子は消費できないため、体内に余分な脂質が残ってしまいます。
肥満との関係
肥満自体も高脂血症の大きな要因です。
体に余分な脂肪がたまることで、血液中の脂質も上昇しやすくなります。
少しのオヤツや食べ過ぎが積み重なって「いつの間にか肥満→高脂血症」という流れになるケースは珍しくありません。
他の病気が隠れている場合
糖尿病、甲状腺機能低下症、副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)など、ホルモンや代謝に関わる病気が原因で高脂血症が起きることもあります。この場合、ただ食事を工夫するだけでは改善しにくく、元の病気にアプローチする必要があります。
年齢やライフステージの影響
年を重ねると代謝が落ち、若い頃と同じ食事でも脂質が処理しにくくなります。
また、避妊・去勢手術後はホルモンの影響で太りやすくなり、それが高脂血症につながることもあります。
ドッグフードで気をつけたいポイント
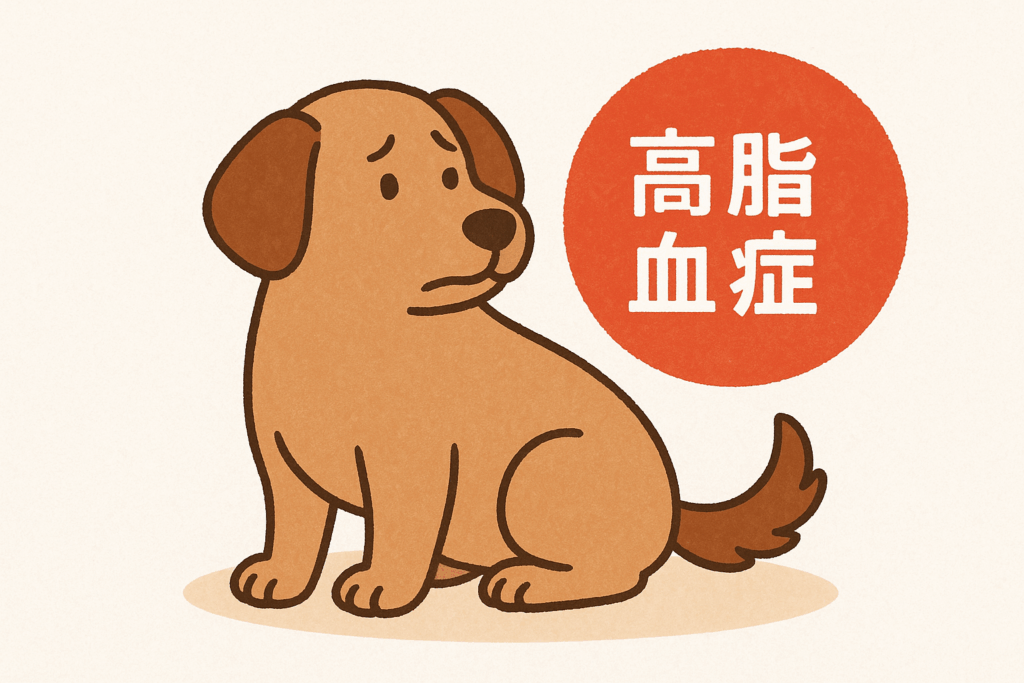
犬が高脂血症と診断されたとき、まず見直したいのが毎日のドッグフードです。
といっても「脂肪が悪いから全部カット!」という単純な話ではありません。
脂質は体を動かすために必要な栄養素でもあるので、ポイントは“量と質のバランス”にあります。
脂肪分の量をチェックする
市販のドッグフードには、成分表に「粗脂肪」と書かれています。
高脂血症の犬には、この数値が低めのフードを選ぶのが基本です。
特におやつやトッピングのチーズや肉の脂身などは、飼い主が気づかないうちに“余分な油”を足してしまう落とし穴になりがちです。
脂質の「質」も大事
同じ脂肪でも、体への影響は違います。
例えば、魚に多く含まれるオメガ3脂肪酸(EPA・DHA)は、血液の流れを整える働きがあるといわれています。逆に、動物の脂身や揚げ物に近い油分は、負担になりやすいと考えられます。
「脂肪=全部悪い」ではなく、質の良い脂を適度に摂れるかどうかがポイントです。
炭水化物や食物繊維とのバランス
脂肪分を減らした分、炭水化物が増えすぎてしまうフードもあります。糖質の取りすぎは肥満や二次的な代謝異常につながるため注意が必要です。また、適度な食物繊維を含むフードは、腸内での脂質吸収をゆるやかにしてくれる役割もあります。
食事の「与え方」も見直す
同じフードでも、与え方ひとつで体への負担は変わります。
・1日分を小分けにして与える(血中脂質の急上昇を防ぐ)
・フードをふやかして消化しやすくする
・おやつや人間の食べ物は極力控える
こうした工夫で、体にやさしい食事習慣を作ることができます。
家庭でできる食事の工夫
高脂血症と診断されると「何を食べさせたらいいの?」と不安になりますよね。
でも、特別なことをするよりも、普段の食事や習慣を少し工夫するだけで愛犬の体への負担をやわらげることができます。
与える量をきちんと管理する
ついお皿いっぱいに入れてしまったり、愛犬が欲しがるからとオヤツをあげすぎてしまったり…。これが脂質やカロリーの過剰摂取につながります。
フードの袋に書かれている給与量を目安にしながら、体重や運動量に合わせて調整していきましょう。
1日分を小分けにして与える
1日2回の食事を3〜4回に分けるだけでも、血液中の脂質が急に上がるのを防ぐことができます。
特にシニア犬や消化に不安がある子には、少量ずつこまめに与える方法がおすすめです。
フードをふやかして消化を助ける
カリカリのままだと、胃や腸に負担がかかることがあります。
ぬるま湯でふやかして与えると、消化がスムーズになり、脂質の処理もしやすくなります。
寒い季節は体も温まり、食欲が落ち気味の子にも食べやすくなります。
低脂肪の食材をトッピングする
いつものフードに、キャベツやブロッコリー、かぼちゃなど野菜を少量トッピングするのもおすすめです。
食物繊維が脂質の吸収をゆるやかにしてくれる効果が期待できます。
脂肪の少ない鶏むね肉や白身魚も良い選択肢です。
ただし量はあくまで「添える程度」にして、フードとのバランスを崩さないことが大切です。
おやつや人の食べ物を見直す
せっかくフードを工夫しても、おやつで脂肪分を取りすぎれば台無しになってしまいます。
ジャーキーやチーズなど脂っこいおやつは控えめにし、与えるならりんごやにんじんスティックなどヘルシーな選択肢に置き換えるのも一つの方法です。
受診を考えるべきサイン
犬の高脂血症は、見た目ではなかなか分かりにくい病気です。
だからこそ「ちょっと気になる変化」を見逃さないことが大切です。
次のようなサインが見られたときは、できるだけ早めに動物病院で相談することをおすすめします。
繰り返す嘔吐や下痢
胃腸がうまく脂質を処理できないと、吐いたり下痢を繰り返すことがあります。
特に白っぽい泡や油っぽい便が出る場合は注意が必要です。
食欲や元気の低下
普段は食いしん坊なのに食べたがらない、散歩に出てもすぐ疲れる…そんな変化も、体に負担がかかっているサインかもしれません。
お腹の痛みや落ち着きのなさ
膵炎を発症すると、お腹をかばうように丸まってじっとしていたり、逆に落ち着きなく歩き回ることがあります。強い腹痛を伴うケースでは、緊急性が高い場合もあります。
健康診断で数値が安定しない
血液検査で中性脂肪やコレステロールの値が繰り返し高いまま下がらないときも、放置は禁物です。
体質によるものか、背景に病気が隠れているのかを見極めてもらう必要があります。
犬の高脂血症関連の論文
参照元:獣医療での脂質代謝治療の現在 2. 診断と解析法,治療水谷尚 /日本獣医生命科学大学獣医内科学教室
引用:
高脂血症の治療の第一歩は,高脂血症の摘発である。
そのためには,日常の診療の中で,疑わしい症例に対して,可能な限りスクリーニング検査を実施することである。
高中性脂肪血症は血清の目視によって肉眼的に診断が可能であるが,高コレステロール血症は生化学的測定を行わない限り摘発が難しい。
また,高脂血症を摘発した場合は,その原因が原発性であるか二次性であるかを鑑別し,適切な治療を行う必要がある。
二次性の高脂血症はもとになる疾病のコントロールが最も重要なポイントとなる。
高脂血症の治療には非薬物療法と薬物療法が有り,食事療法などの非薬物療法を先行して行った上で,それでもコントロール出来ない場合は,適切な薬剤による薬物療法を実施する。(動物臨床医学₂₃(₂)48-₅₃, ₂₀₁₄)高脂血症は,犬の臨床において,もしかしたら最もポピュラーな疾患かもしれない。
しかしながら,その病態が複雑なこと,その危険性が十分に解析されていないこと,検査手法が特殊であること,さらには犬における治療法が確立していないことなどから,なかなか診断・治療にたどり着かないケースも多い疾病と思われる。
要約:
■高脂血症治療の第一歩~まずは「見つけること」から
高脂血症とは、血液の中に「脂のかけら」が多く流れているような状態のこと。普段の生活ではまったく症状を見せないのに、体の中ではじわじわと負担をかけ続ける“静かなトラブルメーカー”です。
犬や猫の場合、健康診断やちょっとした体調不良で受けた血液検査で偶然見つかることが少なくありません。特に 総コレステロール や 中性脂肪(トリグリセリド) の数値を調べておくと、早めに「隠れ高脂血症」を見つけることができます。
■高脂血症は「赤信号」ではなく「黄信号」
高脂血症そのものがすぐに命を脅かすわけではありません。イメージするなら「赤信号で車が止まっている状態」ではなく、「黄信号が点滅して注意を促している状態」に近いのです。
つまり、高脂血症は「すぐに危険!」ではなくても、「このまま進むと事故につながるかもしれない」という警告灯のような存在です。
■背景に隠れていることが多い病気
高脂血症が見つかるとき、多くの場合はそれが“主役”ではなく、“裏方”として別の病気に付き添っています。
たとえば:
・糖尿病 …インスリンの働きが弱くなり、脂質の代謝が乱れる
・クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症) …ホルモンの過剰分泌で代謝バランスが崩れる
・甲状腺機能低下症 …代謝が落ちて脂質を処理できなくなる
・慢性膵炎や肝疾患 …脂肪の分解・利用がスムーズにいかない
つまり「高脂血症=隠れた病気の影」と考えるとわかりやすいでしょう。
■早めに気づくことの意味
もし血液検査で脂質の数値が高いとわかったら、それは「病気そのもの」よりも「体からのSOSメッセージ」と受け止めるのが大切です。
数値をきっかけに、生活習慣や食事内容を見直すこともできますし、背景に潜む病気を早く見つけて治療につなげることもできます。
高脂血症治療の第一歩は薬や特別な療法ではなく、「気づくこと」そのもの。
飼い主さんが血液検査の数値を“ただの数字”ではなく“未来の健康を守るヒント”として受け止めることが、最良のスタートラインになるのです。
まとめ
犬の高脂血症は、最初は目に見える症状がほとんどなく、「気づいたときには数値が高くなっていた」というケースが多い病気です。
しかし、毎日の食事や生活習慣を少し工夫するだけで、愛犬の体にかかる負担を減らすことができます。
ポイントは、
・脂質の量と質のバランスを意識したフード選び
・食事の与え方やオヤツの工夫
・小さな体調の変化に気づいてあげること
この3つです。
「高脂血症」と聞くと不安になるかもしれませんが、決して特別なことをしなければならないわけではありません。飼い主さんがちょっとした工夫を積み重ねるだけで、愛犬の血液はもっと健やかに保てます。
そして何より大切なのは、ひとりで抱え込まず、気になることがあれば早めに動物病院で相談すること。
血液検査の数値は、愛犬からの“隠れたメッセージ”です。
普段の食事と合わせて上手にコントロールしながら、元気な毎日を一緒に過ごしていきましょう。


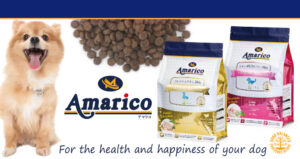

コメント