愛犬がごはんを食べたあと、消化されていないドッグフードをそのまま吐き出してしまう…。そんな場面に驚いたことはありませんか?
一度きりなら様子を見てもよい場合がありますが、繰り返すと心配になりますよね。実は「未消化のまま吐く」にはいくつかの理由が考えられます。この記事では、飼い主さんが知っておきたい原因と、日常でできる工夫についてお伝えします。
犬が未消化のドッグフードを吐くのはなぜ?
犬がフードを未消化のまま吐いてしまうと、「病気なのでは?」と心配になりますよね。
でも実際には、必ずしも深刻なケースばかりではありません。
考えられる原因はいくつかあります。
1.早食いによる吐き戻し
犬は夢中になると、ほとんど噛まずに丸飲みしてしまうことがあります。
胃に一気にフードが入ると、うまく消化が追いつかず、そのまま逆流して口から出てしまいます。
特に食欲旺盛な子や小型犬に多く見られます。
2.ドッグフードが体に合っていない
消化に時間のかかる原材料が含まれていたり、犬の体質に合っていなかったりすると、胃腸に負担がかかりやすくなります。
その結果、消化が始まる前に吐き戻してしまうことがあります。
3.食べすぎ・水の飲みすぎ
空腹のあまり勢いよく食べたり、水を大量に飲んだ直後にフードを食べると、胃の中が急に膨らんで消化がうまくいかず、未消化のまま吐いてしまうことがあります。
4.食後すぐの激しい運動
ごはんを食べた直後に走り回ったり、はしゃいだりすると、胃に負担がかかりフードが逆流してしまうことがあります。
5.消化器系の不調や病気
繰り返し吐いたり、吐いたものに血や黄色い液体が混じる場合は、胃や腸など消化器系のトラブルの可能性もあります。
単なる吐き戻しではなく「嘔吐」に近い状態で、この場合は動物病院での診察が必要です。
家庭でできる対策・工夫
犬が未消化のフードを吐く原因には、飼い主さんが日常の工夫で防げるものも多くあります。
次のような方法を取り入れてみましょう。
1.早食い防止の工夫
一気に食べてしまう子には、早食い防止用の凸凹のついた食器や、フードを小分けにして与える方法が有効です。
お皿の形を変えるだけでも、噛む回数が増えて吐き戻しを防ぎやすくなります。
2.フードの粒の大きさや硬さを見直す
粒が大きすぎると噛まずに丸飲みしやすく、逆に小さすぎても飲み込みやすくなってしまいます。
今のフードが合っていないと感じたら、粒の大きさや硬さを調整してあげるのも方法です。
ぬるま湯でふやかすと消化もラクになります。
3.食事の量や与え方を工夫する
一度にたくさん食べると吐き戻しやすいので、朝・夕に分けるだけでなく、3回に分けるなど少量ずつ与えると負担が減ります。
また、食後すぐに水をがぶ飲みさせないように注意しましょう。
4.食後は安静にする
ごはんを食べたあとは30分〜1時間ほどゆっくり過ごさせ、走り回らせないようにすることが大切です。
散歩も食後すぐではなく、少し時間をあけてから行くと安心です。
5.フード以外の要因にも目を向ける
ストレスや環境の変化も消化に影響することがあります。
落ち着いて食事ができる場所を用意してあげたり、生活リズムを整えることも効果的です。
注意が必要な吐き方のサイン
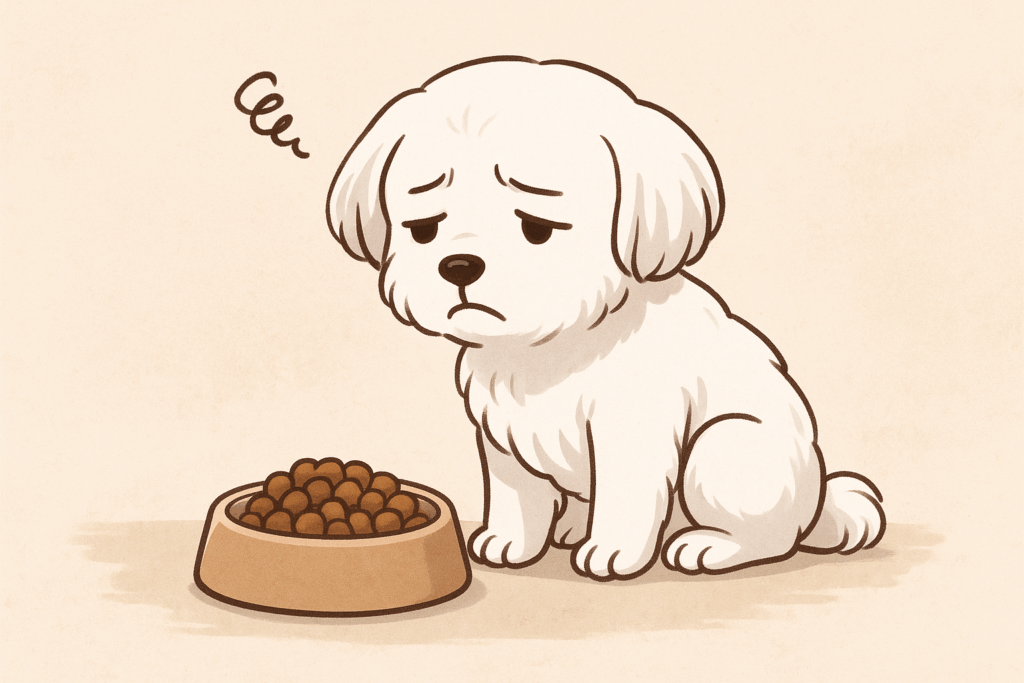
犬が未消化のドッグフードを一度だけ吐いた場合は、食べ方や一時的な体調によることも多く、すぐに大きな心配はいらないケースもあります。
ですが、中には病気のサインが隠れていることもあるため、以下のような症状が見られたら注意が必要です。
1.繰り返し吐く
何度も続けて吐いたり、毎日のように吐き戻す場合は、消化器系にトラブルがある可能性があります。
2.吐いたものに血や黄色い液体が混じる
血が混じっている場合は胃や腸に炎症や出血の疑いがあります。
また、黄色い液体(胆汁)が混じっている場合も消化器系の不調を示していることがあります。
3.元気や食欲がない
普段は食欲旺盛なのに急に食べなくなったり、元気がなくぐったりしているときは要注意。
単なる吐き戻しではなく、体調不良が背景にあるかもしれません。
4.下痢や発熱を伴っている
吐き戻しに加えて下痢や発熱があるときは、感染症や消化器系の病気の可能性も考えられます。
5.子犬や老犬が吐く場合
体力の少ない子犬や老犬は、軽い嘔吐でも脱水や体調悪化につながりやすいため、早めの受診が安心です。
まとめ
犬が未消化のドッグフードを吐くのは、決して珍しいことではありません。
早食いや食べすぎ、水のがぶ飲みといった日常のちょっとした習慣が原因になっていることも多く、食べ方や与え方を工夫するだけで改善するケースも少なくありません。
ただし、吐く回数が多い、血や黄色い液体が混じる、元気や食欲がなくなるといった場合は注意が必要です。
単なる吐き戻しではなく、体調不良や病気のサインである可能性もあるため、早めに動物病院で相談するようにしましょう。
愛犬の様子をよく観察し、「よくあること」と「病気のサイン」を見分けることが、安心して暮らすための第一歩です。


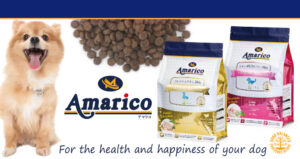


コメント