愛犬の皮膚がベタついたり、フケが目立つようになった…その症状、もしかすると「脂漏症」が原因かもしれません。脂漏症は皮脂の分泌異常によって起こる皮膚トラブルで、フードによって症状が緩和されるケースも。この記事では「食事からのアプローチ」にフォーカスし、皮膚バリアを支える栄養やドッグフード選びのヒントをお届けします。
脂漏症とは?皮脂の異常で起こる皮膚トラブル
犬の「脂漏症(しろうしょう)」は、皮膚から分泌される皮脂の量や質が異常になり、皮膚や被毛の状態が乱れる病気です。
皮脂は本来、皮膚を保護し乾燥や細菌の侵入を防ぐ大切な役割を持っています。
しかし、分泌が多すぎたり、逆に少なすぎたりすると、皮膚環境が崩れてトラブルが起こります。
脂漏症には大きく分けて2つのタイプがあります。
油性脂漏症(ベタつき・臭い・脂の塊)
油性脂漏症は、その名の通り皮膚や被毛が常に油っぽくベタつくのが特徴です。
撫でたときに手にぬるっとした感触が残ったり、毛束が固まってしまったりします。
さらに、皮脂が酸化することで特有の強いにおいが発生し、「犬臭さ」とは違う、油っぽい酸っぱいような匂いがすることも多いです。
進行すると、毛の根元や皮膚のしわ部分、耳の入り口などに黄色や茶色の脂の塊がこびりつくことがあります。
こうした皮脂のかたまりは、マラセチア菌や細菌の温床になりやすく、かゆみや赤み、炎症を引き起こす原因にもなります。
原因としては、ホルモンバランスの乱れやアレルギー、皮膚感染、食事の脂質過多などが関係する場合があります。
特に皮脂の分泌が多い犬種や、耳や皮膚のしわが多い犬では発症しやすい傾向があります。
油性脂漏症は、見た目やにおいの問題だけでなく、皮膚全体の健康悪化につながるため注意が必要です。
日々の観察で「ベタつき」や「独特の匂い」に気づいたら、早めに皮膚環境を整えるケアや食事の見直しを始めることが大切です。
乾性脂漏症(乾燥・フケ・かゆみ)
乾性脂漏症は、皮膚の水分や皮脂が不足し、カサカサと乾燥してしまうタイプの脂漏症です。
毛の間から細かい白いフケが落ちてくるのが特徴で、黒い毛色の犬だと特に目立ちます。
乾燥によってかゆみが強くなり、犬がしきりに体をかいたり、床や壁にこすりつける行動をすることもあります。
フケが舞うだけでなく、かき壊しによる赤みや小さな傷ができやすく、そこから雑菌が入り込んで炎症を起こすこともあります。
皮膚が薄くなったり、毛並みがパサついたりと、見た目にも元気がない印象を与えてしまいます。
背景にあるのは、皮膚のバリア機能の低下です。
本来、皮膚は皮脂と水分によって覆われ、外部の刺激や細菌から守られています。
しかし、このバリアが弱くなると、ちょっとした刺激や乾燥した空気でも皮膚がダメージを受けやすくなります。
栄養バランスの偏り、加齢、ホルモンの変化、アレルギー、そして慢性的な乾燥環境などが原因になることがあります。
乾性脂漏症は「ただのフケ」と見過ごされがちですが、放置すると慢性化し、かゆみや炎症の悪循環を招きます。
皮膚の潤いを保つ栄養やケアを意識し、バリア機能を取り戻すことが改善への第一歩です。
脂漏症に関わる主な原因(後天的要因として)
犬の脂漏症は、生まれつきの体質や遺伝によって起こる場合もありますが、成長してから生活環境や体調の変化によって発症する「後天的な原因」も多く見られます。後天的な要因は、日々の暮らしや食事内容、病気の影響など、飼い主さんの工夫や対策で改善できる可能性があるものです。
ドッグフードの栄養バランスの乱れ(脂質や品質の偏り)
脂漏症の原因のひとつに、毎日食べているドッグフードの栄養バランスの乱れがあります。特に、脂質の量や質が偏っていると、皮脂の分泌がコントロールできなくなり、ベタつきや乾燥といった症状を招きやすくなります。
例えば、安価なフードによく使われる酸化しやすい油や、動物性脂肪の質が悪いものは、体内で炎症を引き起こしやすく、皮膚環境を悪化させることがあります。
逆に、脂質を極端に制限したフードも問題です。
皮膚や被毛の健康には適量の良質な脂肪が欠かせず、足りないと乾燥やフケの原因になります。
また、タンパク質の質や消化吸収のしやすさも重要です。
消化しにくい原料や副産物ばかりのフードは、栄養がしっかり吸収されず、皮膚の再生に必要な材料が不足してしまいます。
さらに、ビタミンAや亜鉛、オメガ3脂肪酸など、皮膚バリアを支える栄養素が不足していると、脂漏症の悪化を招きやすくなります。
つまり、脂漏症対策には「低脂肪」や「高タンパク」といった単純な選び方ではなく、脂質・タンパク質・ビタミン・ミネラルがバランスよく含まれ、なおかつ原材料の質が信頼できるフードを選ぶことが大切です。
必須脂肪酸やビタミン・ミネラルの不足(ビタミンA・亜鉛・オメガ3)
犬の皮膚と被毛の健康には、必須脂肪酸やビタミン、ミネラルが欠かせません。
これらが不足すると、皮膚のバリア機能が弱まり、脂漏症のようなトラブルが起こりやすくなります。
まず、オメガ3脂肪酸。
サーモンや亜麻仁油などに多く含まれ、皮膚の炎症を抑えたり、水分を保持して乾燥を防ぐ役割があります。
これが不足すると、皮膚がカサつきやすくなり、かゆみやフケが出やすくなります。
次に、ビタミンA。
皮膚や粘膜の細胞を正常に保つ働きがあり、皮脂の分泌量を適切に調整します。
不足すると皮膚が乾燥して硬くなり、フケや角質の増加を招きます。逆に過剰摂取もよくないため、適量をバランスよく摂ることが重要です。
そして、亜鉛。
皮膚の再生や毛の成長に深く関わり、傷の治りを助けるミネラルです。
不足すると毛がパサついたり、被毛の色が薄くなるほか、皮膚が荒れやすくなります。
特に吸収率の低い亜鉛しか摂れていない場合、慢性的な不足状態になることもあります。
これらの栄養素は、単体で働くというよりも、他の栄養との組み合わせで効果を発揮します。つまり、オメガ3だけを足す、ビタミンAだけを増やすというよりも、日々の食事で総合的にバランスをとることが、脂漏症の改善や予防につながります。
貧弱なフード品質や酸化の進行、手作り・乾燥フードの落とし穴
脂漏症の原因には、フードそのものの品質の低さや、保存状態の悪さも関わってきます。
安価なドッグフードの中には、原材料の質が低く、栄養価よりもコスト重視で作られているものがあります。
こうしたフードは、皮膚や被毛の健康を支える必須脂肪酸や良質なたんぱく質が不足している場合が多く、長く与え続けることで皮膚トラブルの土台を作ってしまいます。
また、フードは時間が経つと油脂が酸化し、栄養価が落ちるだけでなく、体にとって有害な成分が発生します。
特に開封後のドライフードは空気や光、湿気の影響を受けやすく、保存方法次第では数週間で酸化が進むこともあります。
酸化した油は皮膚の炎症を悪化させ、脂漏症を助長するリスクがあります。
さらに、一見健康的に思える手作り食にも落とし穴があります。
栄養計算が不十分なまま与えると、必須脂肪酸やビタミン、ミネラルが不足しやすく、結果的に皮膚が弱くなることがあります。
また、乾燥タイプのフード(ドライフードやフリーズドライ)は保存性が高い一方、水分量が少ないため、犬によっては皮膚の乾燥を招くこともあります。
「とりあえず食べてくれるから」「長持ちするから」という理由だけでフードを選んでしまうと、気づかないうちに皮膚環境を悪化させる原因をつくってしまいます。品質や鮮度、栄養バランスを意識して選び、適切に保存することが、脂漏症予防の基本です。
食物アレルギー・皮膚炎との関連(マラセチア・細菌など)
脂漏症は単独で起こることもありますが、食物アレルギーや皮膚炎と深く関わっているケースも少なくありません。
特に、アレルギー反応や皮膚の炎症があると、皮脂の分泌バランスが乱れやすくなり、脂漏症の症状が悪化しやすくなります。
食物アレルギーの場合、体が特定のタンパク質や成分を異物とみなし、免疫反応が起こります。
その結果、皮膚にかゆみや赤み、発疹が現れ、犬がかき壊すことで皮膚バリアが壊れ、皮脂分泌がさらに不安定になります。
こうしてベタつきやフケ、強いにおいといった脂漏症の症状が表面化します。
また、皮膚環境の乱れはマラセチア菌や細菌の増殖を招きます。
マラセチア菌は犬の皮膚に元々存在する常在菌ですが、湿気や皮脂が多い環境で一気に増え、強いにおいやかゆみ、ベタつきを引き起こします。
細菌感染も同様に炎症や膿を伴い、症状をさらに複雑にします。
つまり、アレルギーや感染症は脂漏症の「きっかけ」にも「悪化要因」にもなり得るのです。
食事の見直しでアレルギー物質を減らしつつ、皮膚を清潔で健やかな状態に保つケアを同時に行うことが、改善と再発防止の鍵になります。
食事で補いたい栄養素とその役割
脂漏症の改善を考えるとき、スキンケアだけでなく、体の中から皮膚環境を整えることが大切です。そのためには、毎日の食事で必要な栄養素をしっかり摂ることがポイントになります。ここでは、脂漏症のケアに役立つ主な栄養素と、その働きをご紹介します。
オメガ3・オメガ6脂肪酸
鮭やイワシなどの青魚、亜麻仁油、鶏脂などに多く含まれる必須脂肪酸です。皮膚のうるおいを保ち、外部刺激から守るバリア機能を強化します。炎症をやわらげる作用もあるため、かゆみや赤みの軽減にも役立ちます。
ビタミンA
レバーや卵黄、緑黄色野菜などに含まれ、皮脂の分泌バランスを整える栄養素です。過剰な皮脂によるベタつきや、乾燥によるフケの発生を抑える働きがあります。皮膚や被毛の健康維持には欠かせません。
亜鉛
牡蠣や赤身肉、かぼちゃの種などに多く含まれるミネラルで、皮膚細胞の新陳代謝をスムーズにします。亜鉛不足になると皮膚の修復力が低下し、トラブルが長引く原因になるため、日々の食事での補給が重要です。
良質なたんぱく質
肉、魚、卵、大豆製品などに含まれるたんぱく質は、皮膚や被毛の材料となる基本栄養素です。質の良い動物性たんぱく質をしっかり摂ることで、傷んだ皮膚の再生を助け、健康な被毛の育成にもつながります。
これらの栄養素をバランスよく摂ることで、脂漏症の症状を和らげ、再発しにくい健やかな皮膚環境を保つことができます。ドッグフードを選ぶ際は、原材料や成分表をよく確認し、これらの栄養素がしっかり含まれているものを選びましょう。
ドライフードとの付き合い方と改善策
脂漏症のある犬にとって、毎日の食事は皮膚の状態を大きく左右します。なかでもドライフードを常食している場合、便利さの一方で注意したい点があります。
ドライフードは水分がほとんど含まれておらず、長期保存できるよう加工されています。その過程で、使われている脂質の質が酸化しやすくなったり、加熱によって一部の栄養素が壊れてしまうことがあります。こうした要因が積み重なると、皮膚のうるおいが保ちにくくなり、脂漏症の症状が悪化するケースも見られます。
「低脂肪フードを選べば安心」と考える方もいますが、実はそれだけでは解決できない場合も多いです。脂漏症の改善には、ただ脂肪分を減らすのではなく、必要な種類の脂質をしっかり摂ることが大切です。特に、皮膚のバリア機能を守るオメガ3やオメガ6脂肪酸は不足しやすく、これがかゆみやフケ、ベタつきの原因になることもあります。
改善策としては、ドライフードを与える場合でも、鮭やイワシなどの魚油、亜麻仁油、鶏の皮など、良質な脂質をトッピングとして加えるのがおすすめです。また、ドライフードだけでなく、ウエットフードや手作り食を時々組み合わせて、水分や生の栄養を補うのも有効です。
つまり、ドライフードは悪者ではありませんが、「それだけ」で完結させるのではなく、質の良い脂質と水分を意識して補ってあげることが、脂漏症改善のための食事管理のポイントです。
散歩やシャンプーなどの生活習慣と連携させる
脂漏症の改善には、食事だけでなく、日々の生活習慣を整えることも欠かせません。とくに散歩やシャンプー、室内環境の管理は、皮膚の状態を長く安定させるための大事な要素です。
まず、シャンプーは「しっかり皮脂を落とす」ことと「落としすぎない」ことのバランスが重要です。脂漏症の場合、皮脂の質や量が乱れているため、保湿効果のある犬用シャンプーを使って、余分な皮脂や汚れをやさしく洗い流しましょう。洗ったあとは、保湿ローションやスプレーなどでスキンケアをプラスすることで、乾燥によるかゆみやフケを防ぎやすくなります。
湿度管理も見落とせないポイントです。エアコンや暖房で室内が乾燥すると、皮膚のバリア機能が低下しやすくなります。加湿器を活用して、湿度50〜60%程度を保つと皮膚トラブルの予防につながります。
また、シャンプーの頻度も犬の皮膚状態に合わせて見直しましょう。脂っぽさやにおいが気になるからと毎日洗ってしまうと、かえって皮膚を守る皮脂まで奪ってしまうことがあります。週1回〜10日に1回程度を目安にしつつ、獣医師の指示や季節によって調整するのがおすすめです。
そして、散歩は血行を促し、新陳代謝を活発にして皮膚の再生を助けます。軽い運動でも続けることで免疫力が高まり、脂漏症の悪化を防ぎやすくなります。
つまり、脂漏症ケアは食事だけで完結せず、適切なシャンプー・湿度管理・運動といった日常習慣とセットで行うことが、症状改善への近道になります。
脂漏性皮膚炎について
脂漏性皮膚炎
引用元:脂漏性皮膚炎
清佳浩 / 中林淳浩|昭和大学藤が丘病院皮膚科
■要旨
脂漏性皮膚炎の発症には、皮脂の異常、内分泌異常、ビタミン代謝異常、癜風菌などの感染、環境因子、ストレスなど様々な因子が関与しているとされている,。
近年、これら因子のうち癜風菌が注目を集めている。
癜風菌は、現在7菌種に分類されているが、各菌種の役割、病原性はまだ確定していない。
今回、脂漏性皮膚炎の診断、鑑別診断、検査、直接検鏡、癜風菌の培養結果、治療について述べた。
Parker-KOH染色を用いた直接検鏡で、脂漏性皮膚炎病巣中に認められる胞子には、球型と卵型があった。
健常人の総皮脂量に関しては、男性で皮脂の高値例が多く、胞子数も男性に有意に多く認められた。
胞子数と皮脂の間には、相関関係は見られなかった。脂漏性皮膚炎の顔面の病巣から Malassezia globosa, Malassez furfurを多く検出した。
抗真菌剤は菌要素陽性例の約80%で有効以上、抗真菌剤使用例のうち著効例ではすべて胞子数が減少した。
抗真菌剤による治療は、ステロイドに比べて再発率が低かった。
今後、脂漏性皮膚炎に対し、ステロイドに比べて局所副作用が少なく、再発しにくい抗真菌剤がより広く用いられるようになることを期待する。■定義
脂漏性皮膚炎は、脂漏部位である頭部、眉間、鼻周囲、耳、胸部正中などに生じる油性の鱗屑を付す比較的境界明確な紅斑を特徴とする疾患で、新生児から乳児期に発症して自然消退する乳児型と、思春期以降に発症し、慢性に経過する成人型とがある)。
原因の詳細は不明だが、皮脂の異常、内分泌異常、ビタミン代謝異常、癜風菌などの感染、環境因子、ス トレスなど多くの因子が関係する疾患とされている。■診断
鑑別診断診断には、まず臨床症状を詳しく観察すること、特に皮疹の分布および性状が重要である。
セブメーターなどを用いた皮脂の測定も診断の助けとなる。また、癜風菌の有無を検鏡で確かめることは、治療の選択の際に有用である。
さらに病理組織検査や治癜経過が診断の確定に必要な症例もある。
本疾患と鑑別を要する疾患には、頭部接触性皮膚炎、尋常性乾癬、アトピー性皮膚炎、頭部白癬、香粧品皮膚炎、膠原病など様々な疾患がある。
これらの疾患との鑑別のために、症例によりIgEの測定や直接検鏡、パツチテスト、自己抗体の検索などを行う。これら疾患の中では、頭部に限局した尋常性乾癬と本症との鑑別が一番難しい。■脂漏性皮膚炎の病理組織
毛孔部に錯角化、痂皮形成を認める。
症状が高度な症例では、角層中に好中球が認められる。
表皮肥厚があり、表皮内に主にリンパ球からなる細胞浸潤と部分的な海綿状態を認める。
真皮乳頭層の軽度の浮腫と血管拡張、リンパ球主体の中等度の細胞浸潤を伴なう。■癜風菌
癜風菌の本症への関与については、Unnaが1887年に脂漏性皮膚炎を定義したとき、すでに角層中に菌要素があることを記載している。
癜風菌は、皮膚特に脂漏部位に常在する真菌であるが、癜風・Pityropsporum (マラセチア)毛包炎の原因菌でもある)。
また、脂肪製剤の投与を受けている新生児における敗血症の起因菌として注目されてきている。
さらに脂漏性皮膚炎、尋常性乾癬、アトピー性皮膚炎などに関与するとされている。
近年、イミダゾール系抗真菌剤が脂漏性皮膚炎に有効であるという報告が相次ぎ、最近では、本菌が脂漏性皮膚炎の発症に重要な役割を演じていると考えられるようになった。
癜風菌の菌種については、1990年まで、Malassez furfurと Malassezia pachydermatis の2菌種のみが認められていたが、1990年にSimons & Guchoが Malassezia sympodialis を分類し、1996年にGuchoらによって新たに Malassezia globosa, Malasseziao obtusa, Malassezia restricta と Malassezia slooffiae の4菌種が再分類された。■健常人における癜風菌の検討
常在菌である癜風菌の実態を検討する目的で、当院に臨床実習に来ている医学生、ボランティアで以下の検索を施行した。
皮膚疾患を有する例は除外した。
鼻翼付着部の鱗屑を両面テープで採取し、Parker-KOH染色を施して直接検鏡を行った。
セブメーターにて眉間の総皮脂量を測定し、頭部・顔面・体幹から鱗屑を採取した。
この試料を Dixon 培地で培養 し, Guillotらの方法に準じてTweenテストを行い菌種 を同定した。■ステロイド外用剤や抗真菌剤の臨床効果 ・胞子数の変化 ・再発までの期間
我々の施設での治療例の内、経過が判明している症例において、ステロイド外用剤や抗真菌剤の臨床効果・胞子数の変化・再発までの期間の検討を行った。■結果
●A 直接検鏡所見
Parker-KOH染色を用いた直接検鏡で、病巣中に認められる胞子には、球型と卵型がある。
球型の胞子には、2.5-8μmの胞子と1.5-2.0×2.5-4.0μmの大きさの違う胞子がある。
症例により卵型ばかりが目立つもの、球型主体のものなど様々な所見だった。
Fig. 2には脂漏性皮膚炎病巣中に見られた。
大きさの違う球型胞子、卵型胞子を示した。●B 健常人の性別総皮脂量
健常人の性別総皮脂量をFig, 3に示した。
80以下と皮脂欠乏群の症例が、男16例、女6例、正常域である80~120が男21例、女4例、皮脂過多の120以上では、男14例、女2例であった。●C 健常人の性別胞子数
健常人の性別胞子数は男性に有意に多く、1視野10個以上の例が25例見られ、このうち多くは1視 野30個 以下であった。
1視野10個以下の例は男27例、女11例であった。●D 健常人の性別総皮脂量と胞子数の関係
健常人の性別総皮脂量と胞子数の関係については、Fig. 5に 示したが, 胞子数と皮脂の間には, 相関関係は見られなかった。●E 菌種の同定
菌種の同定については、詳細は省略するが、健常人の顔面ではM. globosa, M. furfur, M, sympodialisがほぼ同数。
躯幹ではM. globosa, M. sympodialisが多いこと。
頭部ではM. globasaが一番多くついでM. sympodialis, M. furfur M. pachydermatis が検出された。
脂漏性皮膚炎の顔面の病巣ではM. globasa, M. furfurが多く検出された。●F 外用後の胞子数の変化と臨床効果
外用後の胞子数の変化と臨床効果について検討した。
Fig. 6にafで示した抗真菌剤使用例では、著効例では胞子数の減少した症例ばかりで、coで示したステロイド使用例では胞子数に変化がないものと減少した例がほぼ同数であった。●G 再発率
再発率に関しては、ステロイド使用例では1カ月以内の再発が65例、1カ月再発なしが19例。
一方、抗真菌剤ではそれと対照的に1カ月以内の再発が12例。
1カ月間再発なしが90例であった。●H 抗真菌剤とステロイド外用剤の比較
抗真菌剤とステロイド外用剤を比較すると、ステロイド外用剤はほぼ100%の症例で紅斑、癜痒、鱗屑などの臨床症状を抑制する。
抗真菌剤は菌要素陽性例のうち約80%に有効で、胞子数はほとんどの症例で陰性になる。
ステロイド外用例では1日から1週間、多くは3~5日で症状の再燃を認める事が多い。
抗真菌剤では1カ月以上皮疹が消失している例が多いという結果を得た。
考按脂漏性皮膚炎の発症には、様々な因子が関与している。
皮脂の異常、内分泌異常、ビタミン代謝異常、癜風菌などの感染、環境因子、ストレスなどである。
皮脂の質的あるいは、量的異常に関しては、コレステロール、トリグリセライドなどが本症で増加しており、一方、スクワレン、遊離脂肪酸が減少しているという。
脂漏性皮膚炎の病理組織に関しては、湿疹と尋常性乾癬の中間に位置するとされており、特異的な変化はないが、毛孔周囲の錯角化、角栓形成は本症に特徴的と思われる。
癜風菌を確認する方法には直接検鏡と培養法がある。
脂漏性皮膚炎、健常人における癜風菌の検鏡法の注意点は、通常の皮膚糸状菌を検鏡するときのようにKOH液のみで検鏡しても、通常の癜風病巣における菌要素と違い、胞子がほとんどで菌糸は少数またはまったく認められない症例が多いため、菌要素は観察しがたい。
そこでParker-KOH染色などを用いて染色する必要がある。
また、直接検鏡では球型で、2.5-8μmの大型の胞子と、1.5-2.0×2.5-4.0μmと中型の大きさの違う胞子が見られる。
小型の卵型胞子も検出される。
数年前までは、球型と卵型は、同じ菌種の発育段階の異なるものとされていたが、新たに再分類された癜風菌の7菌種では、形態的に大型の胞子はM. globosa、中型の胞子はM. furfur、小型の卵型胞子はM. pachydermatis、M. sympodialis、M. restricta、
M. slooffiae、M. furfur に相当するとされる。
脂漏性皮膚炎の皮膚に異なった大きさ、形の胞子が直接検鏡で認められることは、数種類の癜風菌が存在している事を示す所見である。
今回の我々の培養結果では、脂漏性皮膚炎の顔面の病巣からM. globosa、M. furfur が多く検出されたが、主要菌種がどれであるかという確定までは至らなかった。
Leeming ら20)は、前頭部の菌種はM. restricta 95%、M. globosa 40%、M. sympodialis 25%、一方、背部ではM. restricta 10%、M. globosa 75%、M. sympodialis 95%と部位により異なると述べている。
我々の健常人における菌種別の培養成績の詳細は、中林らが近く報告するが、部位によって主要な菌種に違いがあるという点では、Leemingらの報告に準じる結果だった。癜風菌の、脂漏性皮膚炎発症に関与するメカニズムについては、抗真菌剤の外用で皮疹の改善に平行して菌数が減少することが認められている。
さらに菌数の増加は再発に結びつくと言う治療データーがある。
Hayら は正常の表皮に存在する免疫調整機構が癜風菌などの常在菌に対する寛容を許しているのではないかと推測している。
AIDSにおいて、CD4陽性細胞数、病気のステージに比例して本疾患の頻度が高くなることより、癜風菌と免疫システム、特にCD4陽性細胞数が本症の発症に重要であろうとされている。
一方、Parry らは、免疫反応は本症の発現には関与していないと報告している。
今後、新たに再分類された癜風菌の7菌種が、それぞれどのような役割を果たしているのか、主因菌種の確認各々の抗原に対する反応など今まで検討された事項についても新たな菌種ごとに再検討する必要があろう。
本症の治療について、諸外国では、抗真菌剤を含む種々の剤形がすでに用いられている。
我々はステロイド外用剤や抗真菌剤の臨床効果について検討したが、抗真菌剤は菌要素陽性例の約80%で有効以上であり、これまでに報告された成績とほぼ同等であった。
胞子数の変化に関しては、抗真菌剤使用例のうち著効例はすべて胞子数が減少した。
再発率に関しては、ステロイドでは1カ月以内の再発が多く、抗真菌剤では1カ月間再発しない例が多く認められた。抗真菌剤による本症の治療は、ステロイドに比べて、再発率を低下させるという報告が認められ、我々の成績もこれを支持する結果であった。
今後、我が国においても脂漏性皮膚炎に対し、ステロイドに比べて局所副作用が少なく、再発しにくい抗真菌剤がより広く用いられるようになることを期待する。
まとめ
脂漏症の改善には、食事・生活習慣・スキンケアをバランスよく取り入れることが大切です。必要な栄養素を意識した食事で体の内側から皮膚環境を整えつつ、ドライフードの場合は良質な脂質や水分を補う工夫を忘れないようにしましょう。さらに、保湿効果のあるシャンプーや適切な洗浄頻度、湿度管理、適度な運動など、日常のケアを組み合わせることで、皮膚のバリア機能を守り、再発しにくい健やかな状態へと導くことができます。


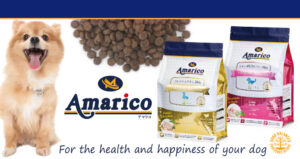

コメント