ドッグフードといえば「チキン」や「ビーフ」が定番ですが、最近では魚を主原料にしたフードが注目されています。
「アレルギーが心配」「お腹にやさしいものをあげたい」「シニア犬にも合う食事を探している」
──そんな飼い主さんの声から、魚ベースのフードは広がりを見せています。
魚ベースのドッグフードが選ばれる理由
最近、魚を主原料にしたドッグフードを選ぶ飼い主さんが増えてきました。
それには、ちゃんと理由があります。
まず大きなポイントは、「お腹にやさしい」ということ。
魚は肉類に比べて消化しやすいと言われていて、お腹が弱い子やシニア犬にも合いやすいんです。
便が安定しなかったワンちゃんが、魚ベースのフードに変えたら改善した、なんて話もよく聞きます。
さらに、アレルギー対策としても魚は注目されています。
チキンやビーフといった定番のタンパク源にアレルギー反応を起こす犬は意外と多く、そうした子にとっては魚が頼れる代替選択肢になることがあります。
それだけではありません。
魚には、DHAやEPAなどのオメガ3脂肪酸が豊富に含まれていて、これがまた体に良い。
毛艶がよくなったり、皮膚のトラブルが落ち着いたりといった効果を感じる飼い主さんもいます。
そして、実は香りが強いというのも魅力のひとつ。
ドッグフードの食いつきが悪い子でも、魚の香ばしい匂いにつられてよく食べてくれるケースがあるんです。
このように、「健康への配慮」と「美味しさ」のバランスがとれた魚ベースのドッグフードは、さまざまな年代・体質のワンちゃんに選ばれている理由があります。
消化しやすくお腹にやさしい
魚ベースのドッグフードが好まれる理由のひとつが、「消化のしやすさ」です。
魚は、チキンやビーフなどの肉類に比べてたんぱく質の繊維がやわらかく、脂肪もあっさりしているため、胃腸にかかる負担が少ないとされています。
特に、お腹が弱くてすぐ下痢をしてしまう子や、食後に吐いてしまうことがある子には、魚のやさしい消化性が助けになることも多いです。
実際、「肉のフードでは合わなかったのに、魚に変えたら便の調子が安定した」という声もよく聞かれます。
また、シニア犬や病後のワンちゃんなど、体力が落ちている時期には、消化しやすい食事がとても大切。
そういった場面でも、魚を主原料としたフードは選ばれやすい傾向にあります。
そして、消化がうまくいくと、腸内環境も整いやすくなり、結果として体全体の調子も良くなることが期待できます。お腹の調子は、健康のバロメーター。
だからこそ、「魚=お腹にやさしい」は、信頼されているポイントなんです。
アレルギー対策に向いていることも
魚ベースのドッグフードが注目される理由のひとつに、「アレルギー対策として取り入れやすい」という点があります。
一般的に、鶏肉や牛肉、小麦などはアレルゲンとなりやすく、皮膚のかゆみや赤み、耳のトラブルといった症状を引き起こすことがあります。
一方、魚はそれらに比べてアレルゲンになりにくいとされており、食物アレルギーが疑われる犬にも試しやすい素材です。
特に「白身魚」や「サーモン」などを使ったドッグフードは、たんぱく質源を絞ってあるため、体への負担が少なく、アレルギーの原因を見極めたいときにも役立ちます。
また、魚には皮膚や被毛の健康をサポートするオメガ3脂肪酸(EPA・DHA)が豊富に含まれており、かゆみや炎症の緩和を助ける効果も期待できます。
もちろん、すべての犬に魚が合うわけではありませんが、今のフードで肌トラブルが続いている場合には、魚ベースのフードに切り替えることで変化が見られることもあります。
まずは少量から始めて様子を見てみるのが安心です。
必要があれば、獣医師と相談しながら進めていきましょう。
DHA・EPAなどの栄養が豊富
魚ベースのドッグフードが支持されている理由のひとつが、「栄養価の高さ」です。
特に注目したいのが、魚に多く含まれているDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)といったオメガ3脂肪酸。
人間にとっても“体にいい油”として知られていますが、これは犬にとっても同じです。
DHAは、脳の働きをサポートしてくれる栄養素。
記憶力や集中力に関係すると言われていて、成長期の子犬はもちろん、シニア犬の認知機能のケアにも役立つとされています。
一方、EPAは、体の中の“炎症”をおさえる働きがあるとされており、アレルギーや関節のトラブル、皮膚のかゆみなどに悩んでいる子のサポートにもなります。
また、これらのオメガ3脂肪酸は、皮膚や被毛の健康維持にもひと役買っています。
毛ヅヤがよくなったり、フケが出にくくなったりと、見た目のコンディションにも変化が表れやすい栄養素です。
ただし、DHA・EPAは体内で合成しにくい成分なので、食事からしっかりと摂ることが大切です。
特に魚を主原料にしたドッグフードなら、こうした良質な栄養を無理なく取り入れることができます。
健康維持はもちろん、年齢や体調に合わせたケアを考えるうえでも、魚ベースのフードは心強い選択肢です。
シニア犬にも適している理由
年を重ねたワンちゃんは、体のあちこちに変化が出てきます。
若いころと同じフードを与えていても、消化に時間がかかったり、栄養がうまく吸収できなくなったりすることもあります。
そんなシニア犬の体にやさしく寄り添ってくれるのが、魚ベースのドッグフードです。
まず、魚は肉類に比べて消化しやすいと言われています。
胃腸への負担が少ないため、体力が落ちてきたシニア犬でも無理なく食べられるのが大きなポイント。
また、たんぱく質も良質で、筋肉や内臓の維持に必要な栄養素をしっかり補えます。
さらに、魚に多く含まれるDHAやEPAといったオメガ3脂肪酸も、シニア犬にとってうれしい栄養。脳の働きをサポートし、認知機能の低下をやわらげる可能性があるほか、関節の健康維持にも役立つと言われています。
歩き方がぎこちなくなってきた子や、寝ている時間が増えた子にも、そっと手を差し伸べてくれるような成分です。
年齢とともに食の好みが変わることもありますが、魚の風味は好きな子が多く、食いつきがよくなるケースもあります。
毎日の食事が、少しでも楽しみになるように…そんな想いで、シニア期には魚ベースのフードを選ぶ飼い主さんも増えています。
どんな魚が使われている?

魚ベースのドッグフードとひと口に言っても、実際にはさまざまな種類の魚が使われています。
それぞれ特徴があり、ワンちゃんの体質や目的に合わせて選ぶことができます。
たとえば、サーモンはとてもポピュラーで人気のある魚です。
香りが良くて食いつきもよく、DHA・EPAといったオメガ3脂肪酸がたっぷりです。
皮膚や被毛のケアにも向いています。
アレルギー対策としても選ばれることが多く、初めて魚ベースのフードを試すならサーモン入りのものはおすすめのひとつです。
また、白身魚(タラやスズキなど)もよく使われています。
脂肪分が少なくて消化が良く、胃腸の弱い子やシニア犬にもやさしい素材です。
クセがないので好き嫌いのある子にも受け入れられやすい傾向があります。
そのほか、マグロやイワシ、ニシンなどもフードによって使われており、それぞれ栄養のバランスや風味に違いがあります。
イワシやニシンは小さめの魚で、重金属の蓄積リスクが低く、安心感があると感じる飼い主さんもいます。
原材料を見るときには、「魚粉」や「魚ミール」だけでなく、どの魚が使われているかが具体的に記載されているかをチェックするのがおすすめです。どんな魚が使われているかを知ることで、より安心して愛犬に与えることができます。
サーモン、白身魚、イワシなどの特徴
魚ベースのドッグフードに使われる魚にも、それぞれ特徴があります。
どの魚が自分の愛犬に合っているかを知ることで、より体にやさしいフード選びができます。
● サーモン
サーモンは、魚の中でも特に人気が高く、食いつきの良さでも知られています。
香りが豊かで嗜好性が高いため、食が細くなった犬や偏食気味の子にも喜ばれることが多いです。
栄養面では、DHA・EPAが豊富で、皮膚や被毛の健康をサポートしたり、脳の働きを助けたりといった効果が期待できます。
皮膚トラブルやアレルギーが気になる犬にも選ばれることが多く、年齢を問わずおすすめしやすい魚です。
● 白身魚(タラ・スズキなど)
白身魚は、脂肪分が控えめであっさりとした味わいが特徴です。
消化がよく、胃腸の負担が少ないため、シニア犬やお腹が弱い子にも向いている食材です。
香りが控えめなので、においに敏感な犬や、魚の風味が苦手な子でも受け入れやすいのがポイント。
アレルゲンになりにくいこともあり、食物アレルギーが気になる場合の選択肢としても重宝されます。
● イワシ
イワシは小型の青魚で、栄養価が非常に高い魚です。
サーモン同様にオメガ3脂肪酸が豊富で、抗炎症作用や免疫サポートが期待されます。
関節の健康を気づかう犬や、毛ヅヤを整えたい場合にもおすすめです。
さらに、小型の魚なので水銀などの重金属の蓄積リスクが低いという点も安心材料のひとつです。
自然素材や安心素材にこだわる飼い主さんにとっては、イワシを使ったフードは魅力的です。
「フィッシュミール」とは?気になる原材料の読み方
ドッグフードの原材料表示を見ていると、よく出てくるのが「フィッシュミール」(魚ミール)という言葉です。
なんとなく魚っぽいとは分かっても、実際にどんなものなのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。
フィッシュミールとは、魚を原料として加熱・乾燥・粉砕して作られた粉状の原料のことです。
たんぱく質が豊富で、長期保存もしやすいため、さまざまなフードに使われています。
ただし、気をつけたいのはその「質」です。
フィッシュミールには、魚の種類がはっきり記載されているもの(例:サーモンミール、イワシミール)と、単に「フィッシュミール」とだけ書かれているものがあります。
後者の場合、どんな魚が使われているのかがわからず、中には質の低い原料が含まれている可能性も否定できません。
また、製造過程で酸化防止剤や保存料が使われていることもあるため、添加物が気になる方はその点もチェックしておきたいところです。
選ぶときのポイントは、「○○ミール」と魚の種類が明記されているかどうか、そして信頼できるメーカーかどうか。パッケージの表だけでなく、裏側の原材料欄もじっくり読んでみると、より安心して愛犬に与えられるフードが見えてきます。
魚ベースのドッグフードを選ぶポイント
魚ベースのドッグフードといっても、種類はさまざま。
どれを選べばいいか迷ってしまうのは当然です。
愛犬にぴったりのフードを選ぶために、いくつかのポイントを押さえておくと安心です。
1. 使われている魚の種類が明記されているか
まず注目したいのが、どんな魚が使われているか。
パッケージに「フィッシュ」や「魚粉」とだけ書かれているものよりも、「サーモン」「白身魚」「イワシ」など具体的な魚の名前が記載されているフードのほうが安心感があります。
魚の種類によって栄養価やアレルギーのリスクも異なるため、できるだけ中身が明確なものを選びましょう。
2. 魚が主原料になっているか
原材料は使用量の多い順に表示されています。
「サーモン」や「白身魚」が最初のほうに書かれていれば、それだけその魚がたっぷり使われている証拠です。
逆に、最初に「穀物」や「動物性油脂」が来ている場合は、魚の配合量が少ない可能性があるので要チェックです。
3. 添加物や保存料の有無
できるだけ余計なものが入っていない、無添加・無香料・無着色のフードが理想的です。
特に体が敏感な犬や、アレルギー体質の子には、シンプルでナチュラルなものを選んであげると安心です。
4. 愛犬の年齢・体質に合っているか
子犬用・成犬用・シニア用など、ライフステージに合ったフードを選ぶことも大切です。
また、体重管理が必要な犬にはカロリー控えめのもの、皮膚トラブルがある子にはオメガ3脂肪酸が豊富なものなど、目的に合わせた設計かどうかも確認しましょう。
5. 信頼できるメーカーかどうか
最後に、メーカーやブランドの信頼性も大事な判断材料です。
原材料の調達先や製造工程をきちんと開示しているか、過去にリコールやトラブルがないかなども、調べておくとより安心です。
こんな子には特におすすめ
魚ベースのドッグフードは、すべての犬に合うとは限りませんが、特に「これは試してみてほしい!」というタイプの子がいます。
以下のような悩みや特徴があるワンちゃんには、魚ベースのフードがぴったりかもしれません。
● 皮膚トラブルが多い子
かゆみやフケ、赤み、被毛のパサつきなど、皮膚に関するトラブルが気になる場合、魚に多く含まれるオメガ3脂肪酸(DHA・EPA)が心強い味方になります。
炎症をおさえる働きがあり、皮膚や被毛の健康をサポートしてくれます。
● 食物アレルギーが疑われる子
牛肉や鶏肉、小麦などによるアレルギー反応が心配なとき、魚は比較的アレルゲンになりにくいとされています。
特に、たんぱく源を魚に絞ったフードは、アレルギーの原因を見極めたいときにも使いやすい選択肢です。
● シニア期に入った子
年齢を重ねると、消化機能が落ちてくる子もいます。
魚は消化しやすく、胃腸に負担をかけにくいため、シニア犬にもやさしい素材です。
さらに、脳や関節のサポートにもなる栄養が含まれており、年齢に合わせたケアにもぴったりです。
● 食いつきが悪い子・偏食気味な子
魚の香りや風味が大好きなワンちゃんは意外と多く、サーモンやイワシなど香りが強めの魚を使ったフードは食欲をそそると言われています。
食が細くなってきた子や、なかなかドッグフードを食べてくれない子にも試してみる価値はあります。
魚ベースでも気をつけたいポイント
魚ベースのドッグフードは栄養価も高く、アレルギーや皮膚トラブルにも配慮されたものが多いため、「体にいいフード」というイメージを持たれがちです。
たしかに魅力の多い選択肢ですが、だからといって「魚なら何でもOK」ではないという点には注意が必要です。
まず気をつけたいのは、原材料の表示です。
たとえば、「フィッシュミール」や「魚エキス」とだけ書かれていて、魚の種類がはっきりしていないものは注意が必要です。
何の魚が使われているかわからないと、アレルギー対策としても不十分ですし、品質も読み取りにくくなります。
また、酸化の問題も見逃せません。
魚に含まれる脂肪(特にオメガ3脂肪酸)は非常にデリケートで酸化しやすく、劣化すると体に良くない影響を与える可能性があります。
袋を開けたら、なるべく早めに使い切ること、保存状態に気をつけることが大切です。
密閉容器を使ったり、冷暗所に保管したりといったひと手間が、フードの鮮度を保ちます。
さらに、魚にアレルギーがある子もいるという点も忘れてはいけません。
魚=低アレルゲンというイメージはありますが、すべての犬にとって安全とは限りません。
もし魚ベースのフードに切り替えて、逆にかゆみや体調不良が出るようであれば、すぐに中止して獣医師に相談を。
最後に、どんなに良いフードでも「そればかり」にならないことが大切です。
栄養が偏らないように、体調や年齢に合わせてフードの見直しをしていくことも、飼い主さんの大切な役割です。
魚介類に含まれるチアミナーゼと犬について
引用元:禁忌食(その4)──魚介類(チアミナーゼ)
左向敏紀・大島誠之助
■はじめに
チアミン(ビタミンB1)欠乏症はヒトでは脚気を呼ばれ、
主に下肢に起こる多発性神経炎である。(略)■チアミン(ビタミンB1)とは
チアミンは体内に入るとチアミン2リン酸(thiamindiphosphate:TDP)という補酵素となり、ビルビン酸デヒドロゲナーゼ(解糖系とクエン酸回路間)、
α-ケトグルタール酸デヒトロゲナーゼ(クエン酸回路内)、
トランスケトラーゼ(ベントースリン酸経路)の3種類の酵素の働きを制御することで、
炭水化物代謝や脂質代謝、アミノ酸代謝にかかわっている。
脳への唯一のエネルギー源であるブドウ糖の代謝にチアミンが必須であり、
脳機能改善へ寄与するといわれているため、現在では、様々な食品へのチアミン強化、
サプリメントによる補充がなされている。
また、チアミンは神経伝達物質であるアセチルコリンの合成にも関与している。■最小栄養所要量
哺乳動物においては、チアミンを体内合成できないために食事からの摂取が必須である。
成犬の維持きのための最小栄養所要量は、100kcalあたり29μgである。(Association of American Feed Control Officials[AFFCO].Official Publication,1999分より引用)。
チアミンは主に炭水化物、脂質、アルコール代謝に必要とされるため、エネルギー消費増加に伴い必要量が増加ずる。
それゆえ欠乏症の問題の方が多く、過剰症の報告はない。
ヒトでは、経口や経静脈的に通常必要量の3倍以上の量を投与されても全く無害であるといわれている。
経口投与では大部分が排泄され、経静脈投与されても余剰分は速やかに排泄される。
食事の質が急に悪くなる、摂食量低下や消化吸収能力の低下、利尿剤などの薬剤投与によるチアミンの体外排出の増加など、チアミン欠乏症は他の多くのビタミンと比べて比較的早期に現れる栄養性欠乏症である。■供給源
現在では、ほとんどの市販ペットフード中にチアミンが充分含まれている。
最も豊富なチアミン供給源は全粒穀物、酵母や肝臓(特にブタの肝臓)である。
チアミンは科学的に非常に不安定であり、ペットフード中に使用されるチアミン成分は、チアミン塩酸塩やチアミン硫酸塩が最も一般的である。■注意すべき食材
犬猫でのチアミン欠乏症は現在ではほとんど見られない。
なぜなら、市販のフード中には充分量のチアミンが補われているからである。
そのため、チアミン拮抗物質の多量摂取に注意する必要がある。
チアミン分解酵素であるチアミナーゼ(アノイリナーゼともいう)が多く
含まれるものとして、魚介類、甲殻類が一般的である。
また、ワラビ、ぜんまいなどのシダ類、細菌、真菌、酵母にもチアミナーゼが
豊富に含まれている。
チアミナーゼは酵素であるため、熱処理を行えば失活するので、これらを生で与えないことが重要である。
炭水化物ばかりを摂取することもチアミン欠乏症を引き起こす原因である。
チアミンは哺乳動物では体内合成できないため、食事からの摂取が必須である。
そのため、栄養バランスの偏りでチアミン摂取量が不足すること、炭水化物代謝によってチアミン消費が増加することでチアミン欠乏症に陥る。
ヒトではグルコースによる高カロリー輸液療法の際に急性のチアミン欠乏症となることがわかっており、ビタミンの充分な補充が行われる。■臨床症状(チアミン欠乏症)
よく「猫にイカ刺しを与えると腰を抜かす」と耳にするように、チアミン欠乏症は犬と比べて猫に多く見られる。
これは、猫のチアミン必要量が犬よりも多いためである。
また、生の魚介類にチアミン分解酵素であるチアミナーゼが多く含まれるため、魚を摂取する機会が多いことも原因の一つといえるだろう。
臨床症状は、初期には食欲低下、成長不良、唾液分泌過多が見られる。
その後、頭部と頸部の腹側への屈曲、短い緊張性の痙攣発作、眼振、多発性神経炎、心肥大(犬に多い)。運動機能障害、立位反射消失、不全麻痺が出現する。
この病気に経口または経静脈的にチアミン投与治療(2~4mg/kg/day)を行えば、24時間以内に全ての症状が改善する。
しかし、治療を実施しなければ、伸筋硬直、次いで昏睡となり、これら末期症状の発現から48時間以内に死に至る。■ウェルニッケ脳症
チアミン欠乏による中枢神経系の脳症のことで、ヒトではしばしば過度のアルコール摂取で起こることがある。
これは、偏食によるチアミン摂取不足と、利尿によるチアミン喪失が主な原因であるため、高齢者や妊婦における低栄養摂取や、医原性でも起こりうる。
急性期には眼球運動障害、運動失調、意識障害が3主要症状で、自覚症状として多いのは、複視やめまい、注意力散漫、傾眠、慢性期になると見当識障害、健忘症などが発現する。■大脳皮質壊死症
牛や緬羊、山羊などの反芻獣では、チアミン欠乏によって糖エネルギー依存症の高い大脳皮質の壊死が起こる。
反芻獣では、通常、第一胃内微生物によってチアミンが合成され、また、飼料にも充分量のチアミンが強化されているため、チアミン欠乏症は起こりにくいとされている。
しかし、第一胃機能の未熟な若齢個体では第一胃内で異常発酵が起こり、微生物によるチアミン合成が低下しチアミン欠乏に陥る。
異常発酵はチアミナーゼ産生菌の増殖も引き起こすため、チアミン欠乏状態にさらに拍車をかける。
また、濃厚飼料の多給、粗飼料の不足、カビなどの生えた飼料を与えることでも、第一胃内環境が変化して異常発酵が起こる。
症状は歩様異常、盲目、眼振、痙攣、弓なり緊張、起立不能、失神、昏睡が現れる。
症状が急性、重度な場合は早期に治療を開始しなければ2、3日で死に至る。■まとめ
・チアミンは主に炭水化物代謝に重要な補酵素である。
・哺乳動物ではチアミンを体内合成できないため、食事からの摂取が極めて重要である。
・現在では、ほとんどの市販ペットフードにチアミンが十分量含まれているが、チアミナーゼを豊富に含む食材の長期摂取や、偏食、食事摂取量低下に注意する必要がある。
・チアミン欠乏症は早期発見、早期治療が重要であり、速やかに適切な治療がなされない場合、2、3日で死に至る。
まとめ
魚ベースのドッグフードは、アレルギー対策や皮膚・被毛の健康維持、消化のしやすさといった点から、多くの飼い主に注目されています。特にサーモンや白身魚には、良質なたんぱく質やオメガ3脂肪酸が豊富に含まれており、愛犬の体調を内側からサポートしてくれます。
選ぶ際には、原材料の表記をよく確認し、「主原料が魚」であること、添加物が少ないこと、信頼できるメーカーの商品であることがポイントです。
ただし、すべての犬に合うとは限らないため、初めて与える際は体調の変化に注意しながら少しずつ試すことが大切です。
愛犬の健康とライフステージに合ったフードを選ぶことで、より健やかな毎日をサポートできます。
魚ベースのドッグフードは、その選択肢のひとつとして、ぜひ前向きに検討してみてください。


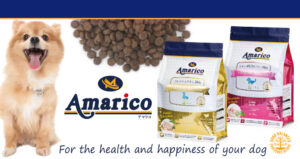
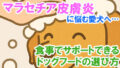

コメント