犬の皮膚トラブルで多いのが「マラセチア皮膚炎」です。ベタつきや赤み、においなどが気になるこの皮膚炎、じつは毎日の食事が悪化や改善に影響することも。本記事では、マラセチアに悩む愛犬のためにどんなドッグフードを選べばよいか、その考え方やポイントをわかりやすく解説します。商品紹介ではなく、選び方の軸をお伝えする内容ですので、どのブランドを選ぶ際にも役立ちます。
マラセチア皮膚炎とは?
「最近、うちの犬が体をよくかいている」「皮膚がベタついて赤くなってきた」
そんな症状が続いているときに、よく疑われるのがマラセチア皮膚炎です。
マラセチアとは、『犬の皮膚や耳の中などに普段から存在している常在菌(カビの一種)』のこと。
ふだんは悪さをせずにおとなしくしているのですが、皮膚が蒸れたり、免疫力が落ちたり、体質が変わったりすることで異常に増殖してしまい、炎症を引き起こします。これが「マラセチア皮膚炎」です。
主な症状
マラセチア皮膚炎の症状には、次のような特徴があります。
・皮膚が赤くただれている
・かゆみが強く、しょっちゅうかいたり舐めたりしている
・独特の「脂っぽいにおい」がする
・ベタベタしてフケのような皮脂が出る
・耳が汚れて、黒っぽい耳垢が出ることも
とくに脇の下、股、首の周り、指の間など、湿気がこもりやすい場所に出やすいのが特徴です。
なぜマラセチアが増えるの?
もともと皮膚にいるマラセチア菌が、なぜ急に悪さをするのか——
その原因はひとつではありませんが、代表的な要因としては次のようなものがあります。
・皮膚が脂っぽくなって菌が増えやすくなる
・アレルギー体質で皮膚のバリアが弱っている
・湿気や汚れによる蒸れ
・ストレスや加齢、ホルモンバランスの乱れ
・食事内容が体質に合っていない
こうしたことが重なると、マラセチア菌が爆発的に増えて、皮膚がかゆくなったり炎症を起こしたりするのです。
早めの対応が大切
マラセチア皮膚炎は慢性化しやすく、自然に治ることはあまりありません。見た目は一見「ただの皮膚トラブル」のように見えるので放置されがちですが、早いうちに対処することで悪化を防げます。
かゆがる、赤みがひかない、皮膚がベタついてきた——そんなサインを見逃さないようにしましょう。
どんな症状が出る?
マラセチア皮膚炎の症状は、見た目の変化もありますが、「かゆがり方」や「におい」など、日常のちょっとした変化にあらわれることも多いです。最初は軽いかゆみから始まり、放っておくとだんだん悪化していきます。
「うちの子、最近よく体をかいてるな…」
そんなふうに感じたら、以下のような症状が出ていないか注意して見てあげてください。
よく見られる症状
・しつこいかゆみ
四六時中、かいたり舐めたりしていませんか?特に脇の下や足の付け根、耳の周り、口の周りなどを気にするようになります。かく場所が毎回同じだったり、眠れないほどかゆそうだったら要注意です。
・皮膚が赤くなっている・ただれている
毛をかき分けて見ると、赤く炎症を起こしていたり、皮膚がジュクジュクしている場合もあります。かゆみで引っかいたり、舐めすぎたりして悪化しがちです。
・ベタつき・皮脂の多さ
触ると皮膚がベタベタしていたり、毛が脂っぽくなっている場合、マラセチア菌が増えているサインかもしれません。しっとりを通り越して、べっとりしていたら注意です。
・独特のにおい
いわゆる「脂っぽいにおい」「発酵したようなにおい」が強くなるのも特徴です。普通の犬の体臭とは違い、ちょっとツンとするような、不快なにおいです。耳の中からにおうこともよくあります。
・フケや黒ずみが目立つ
皮膚の表面にフケのようなものが出たり、かき続けたことで色素沈着して黒ずんでくることもあります。
・毛が抜けてくる
炎症やかきすぎで、毛がところどころ薄くなることも。特に耳や足の裏、首まわりなど、こすれやすい部分が目立ちます。
部位にも特徴があります
マラセチア皮膚炎は体の特定の部位に出やすいのもポイントです。とくにこんな場所に症状が出ていれば、マラセチアを疑うきっかけになります。
・耳の中(外耳炎としてもよく見られます)
・口の周りやあご下
・首まわり、脇、股、足の付け根
・指の間や肉球のまわり
・しっぽの付け根やお腹
症状はその子の体質や環境によっても違いますが、「なんだか様子がおかしい」と思ったら早めに皮膚をチェックするクセをつけておくと安心です。
マラセチア皮膚炎は早く気づいてあげるほど治りやすくなります。毎日のスキンシップの中で、ちょっとした変化を見逃さないことが大切です。
原因になるものとは?
何か「結果」があるときには、必ずその「原因(もと)」があります。
たとえば、風邪をひいた。犬がドッグフードを食べなくなった。売上が落ちた。──どんなことでも、背景には“きっかけ”や“もとになるもの”があるんです。
この「もとになるもの」こそが、原因です。
体調が悪くなった場合
原因になるもの:
・冷房の効いた部屋で薄着だった
・寝不足が続いていた
・人混みの中でマスクをしなかった
これらが重なって「風邪をひいた」わけです。
つまり、体調不良の“原因になるもの”は、こうした生活習慣や行動です。
犬がごはんを食べないとき
原因になるもの:
・フードの味が変わった
・お腹を壊している
・ストレスがたまっている
・歯が痛い
このように、「食べない」という結果の裏には、何か理由(原因)になることが隠れているんですね。
なぜ“原因になるもの”が大事なのか?
原因を知らないと、「対策」も「改善」もできません。
ただ現象を見ているだけでは、同じことがまた起きます。
たとえば──
・「売上が落ちた」ときに、値段が高すぎたのか、商品が古いのか、接客が悪かったのか。
・「子どもが勉強しない」ときに、やり方が難しすぎるのか、興味がないのか、怒られすぎたのか。
本当の原因(=原因になるもの)を見つけないと、問題は解決しません。
フードが関係する理由
犬の健康や行動に何か気になる変化があったとき、「もしかしてフードが関係してるんじゃない?」と考えることがありますよね。
これは、単なる思い込みではなく、実際にフードが原因になっているケースは少なくありません。なぜなら、毎日口にするものだからです。人間でいえば、毎日3食のごはんと同じ。それだけ影響力があるんです。
1. 体に合っていない
どんなに良いフードでも、その子の体質に合わなければ意味がありません。
例えば──
・消化がうまくできない(下痢や便がゆるい)
・アレルギーを起こす(かゆみ、耳の赤み、皮膚のトラブル)
・食べたあとに吐いてしまう
こういった症状があるとき、フードが体に合っていない可能性があります。これは人間で言えば、「そばアレルギーの人がそばを食べてしまった」ようなものです。
2. 栄養のバランスが崩れている
最近は手作りごはんやグレインフリー(穀物不使用)の流行もあり、栄養バランスに偏りが出ることもあります。
例えば、タンパク質が足りなかったり、逆に脂質が多すぎたりすると──
・毛づやが悪くなる
・元気がなくなる
・皮膚がカサカサ、ベタベタする
など、見た目や行動にも影響が出ます。
3. 味やにおい、食感の変化
犬は意外とグルメです。
フードの味が急に変わったり、保存状態が悪くなっていたりすると、「これいつもと違う」と感じて食べなくなることがあります。
特に──
・フードの切り替えを急にした
・袋の封がしっかり閉まっていなかった
・湿気やニオイ移りで風味が落ちた
こんなことが原因で、フードへの警戒心が強くなる子もいます。
4. 病気のサインとして表れることも
フードを食べない、急に食欲が変わった…
これが実は病気のサインであることもありますが、最初に気づけるのが「いつものごはんを食べない」ことだったりします。
だからこそ、フードに対する変化には敏感になっておくべきなんです。
イヌのマラセチアと皮膚疾患
引用元:イヌのマラセチアとその関与が予想される皮膚疾患
永田雅彦/ASC皮膚科
■要旨
イヌから分離されるマラセチアは「Malassezia pachydermatis」が主体であり、その関与が予想される『マラセチア皮膚炎』と呼ばれる疾患がある。
皮疹は脂漏性皮膚炎に相当している。
今後、ヒトと動物に共通する疾患として、その相違点を明らかにすることで、
この領域における普遍的病態の理解を深めることが可能と推察された。■イヌから分離されるマラセチア
これまでイヌから分離されるマラセチアは「Malassezia pachydermatis」
だけだと考えられていたが、M.furfur.M.sympodialis など他のマラセチアも分離されることが明らかにされた。M.pachydermatis は健常犬の皮膚、外耳、粘膜などに分布し、皮脂が蓄積しやすい脂漏部位(間擦部、外耳道等)で検出されやすい。
イヌはそれぞれの国や地域において、特定の用途を目的に交配を重ねて作出されている。
バセットハウンドという種は皮脂やしわの多い皮膚を特徴とし、
健常であってもマラセチアを分離する頻度が高い。
またマラセチアの増殖には温度湿度などの環境因子も影響する。
実験施設ではイヌがケージで飼育され、その下に排せつ物が落ち、
これを水洗いするので、比較的多温になることがある。
このような環境で飼育されるビーグルの耳における
マセラチアの寄生数は、健常家庭飼育犬の耳に比べ有意に多い
ことが明らかにされている。
このように、イヌから分離されるマラセチア数は、種、部位、
環境等によってさまざまである。
■イヌの「マラセチア皮膚炎」
1983年、Dufaitは慢性皮膚炎の病態にマラセチアが関与していることを推察した。
しかし、当時常在菌として認知されていたマラセチアは皮膚バリア機能の変調により二次的に増殖しているに過ぎないと反論され、マラセチアの病原性について深い議論に至ることはなかった。
それから10年後、Mason&Evansは、いわゆる脂漏部位に生じる皮膚炎からマラセチアから分離されること、さらにケトコナゾール内服によりこれら皮疹が改善し、マラセチアも消退することを指摘した。
それ以降、本症は「マラセチア皮膚炎」と呼ばれるようになり、その臨床はヒトの脂漏性皮膚炎に相当している。
皮疹は皮表に鱗屑や脂漏を伴う比較的境界明瞭な紅班を特徴とし、慢性経過を辿ると苔癬化や色素沈着を認める(Fig.1)。
本症の組織では真皮血管周囲にリンパ球を主体とした細胞浸潤がみられ、表皮内浸潤も観察される。
また錯角化を伴う不整な表皮肥厚が観察され、73.3%の標本において表皮にマラセチアが検出される。
マラセチアと皮膚炎の病態的関係は明らかにされていないが、健常皮膚よりも皮膚炎から分離された菌においてphospholipase産性能が高いこと、また部位や皮疹によって遺伝型に差があることも報告されている。
本症では外用療法も有用である。
イヌは全身を毛で被われ、されに自分自身の身体を舐める習性があることから膏薬療法を選択する機会は少なく、界面活性剤を基剤とした薬物あるいは消毒剤による治療が汎用とされている。
そのひとつとして2%ミコナゾールと2%クロルヘキシジンを配合したシャンプー製剤があり、わが国で実施されている。
なおシャンプーの効果は主成分による抗真菌作用に限定えず、マラセチア増殖の母地となる皮表脂質の除去も関与する。
先の試験では、対照として脱脂作用を有す1%ニ硫化セレン含有シャンプーが使用され、約50%の効果がみられている。
シャンプー療法は本症に有効であるが、改善に乏しい症例を見逃せない。
非改善霊では皮表に大量の菌要素を認めないにもかかわらず皮膚炎が持続している。
したがって、菌の増殖に依存しない炎症の存在が予想される。
これまで動物皮膚にマラセチア死菌を接種すると脂漏性皮膚炎の組織像を誘発できること、マラセチアがケラチノサイトからサイトカインを産生させることなどが報告されている。
本症に羅漢したイヌにマラセチア抽出液による皮内反応を行うと、即時型陽性反応が34%で認められる。
さらに本試験にて、皮内反応性群では90.5%が脱脂シャンプーで改善したのに対し、皮内反応陽性例は66.7%が1歳齢未満(ヒトの青年期以前)であった。
ちなみに脱脂シャンプーによる非改善例はいずれもケトコナゾール内服にて軽快しその有効性は全身投与による薬剤の確実な組織移行と残効性。あるいは本剤が有している抗炎症作用などが推察される。
推測の域は出ないが、皮内反応陽性の病態的意義として、皮膚炎を誘導しやすいなんらかの皮膚素因の関与が予想される。
最近、表皮に分布するC型レクチンMincleが病原性真菌マラセチアの受容体であること、さらにMincle遺伝子欠損マウスでは、マラセチアを投与して誘起される炎症反応が有意に減少することが報告された。
今後イヌにおいても同受容体あるいは同様の受容体の分布あるいは発現と炎症性サイトカイン産生の関係について検討が必要と思われた。
マラセチア対策で意識したい「食事」のポイント

マラセチア皮膚炎は、犬の耳や皮膚に常在している“マラセチア菌”が、何かのきっかけで増えすぎることで起こります。ベタつき、赤み、強いかゆみ、独特なニオイ——見ている飼い主さんもつらくなる症状です。
この菌は、もともと皮膚にいる常在菌なので、「完全にいなくする」ことはできません。だからこそ大切なのは、菌が増えすぎないような体の環境をつくってあげること。そしてそのために、毎日の食事が大きなカギを握っています。
食べ物は、体の内側からコンディションを整える基本です。どんなにいい薬やシャンプーを使っても、食事が合っていなければ、またすぐに症状がぶり返してしまう。だからこそ、「何を食べているか?」に目を向けてほしいのです。
糖分・炭水化物の量に注意
マラセチア菌が好むのは、糖分(甘いもの)や炭水化物です。つまり、そういった成分が多い食事を続けていると、皮膚の表面で菌がどんどん繁殖しやすい環境になってしまいます。
よくあるのが、以下のようなケースです:
・市販のドッグフードで小麦やトウモロコシが主原料になっているもの
・サツマイモやジャガイモなど糖質の多い食材がたっぷり使われている
・「ワンちゃん用ビスケット」など、甘味料入りのおやつを頻繁に与えている
こうした食事を毎日続けていると、マラセチア菌にとっては“居心地のいい環境”になります。もちろん、炭水化物や糖分を完全にゼロにする必要はありませんが、量を抑えることは意識したいところです。
最近では、穀物を使っていない「グレインフリー」タイプや、ジャガイモや芋類を減らした「低糖質フード」も増えてきています。症状が出ている子には、そういったフードに切り替えてみるのもひとつの方法です。
また、手作りごはん派の方は、ついつい使ってしまいがちな白米やイモ類の量を見直すのも大切です。体にいいと思って与えていたものが、実は皮膚トラブルの原因になっていることもあるんです。
オメガ3脂肪酸など皮膚サポート成分
犬の皮膚トラブル、とくにマラセチアやアレルギーによるかゆみ・赤みなどがあるとき、「体の外からのケア(薬やシャンプー)」はもちろん大切ですが、内側からのサポートも見逃せません。
そこで注目されているのが、オメガ3脂肪酸などの“皮膚サポート成分”です。
オメガ3脂肪酸ってなに?
オメガ3脂肪酸は、魚の油や亜麻仁(あまに)などに含まれている良質な脂(あぶら)のこと。
代表的なものに、「EPA」や「DHA」という成分があります。これらは、体の中で炎症を抑える働きをしてくれるんです。
皮膚の赤み、かゆみ、ベタつき——これらの症状は、皮膚の中で「軽い炎症」が起きていることが多いので、オメガ3をとることで自然とおさまっていくケースがあるんですね。
こんなときにおすすめ
・皮膚がカサカサしている
・被毛がパサついている
・赤みやかゆみがよく出る
・耳が脂っぽくてにおう
・アレルギーやマラセチアが気になる
こういった子には、オメガ3をふくむフードやサプリを取り入れると、体の中から皮膚のコンディションが整いやすくなります。
ほかにもある皮膚サポート成分
オメガ3以外にも、皮膚を助ける成分はたくさんあります。たとえば:
・亜鉛:皮膚の修復をサポートしてくれる
・ビオチン(ビタミンBの一種):健康な毛づやを保つために必要
・ビタミンE:皮膚の老化を防ぐ、抗酸化の働きがある
・セラミド:皮膚のバリア機能を強くする
こうした成分は、単体でサプリとして売られているものもありますし、皮膚サポートに特化したドッグフードにバランスよく入っていることもあります。
与えるときのポイント
ただし、「体にいいから」といって与えすぎはNGです。
とくに脂肪分は過剰になると、逆に下痢になったり、肝臓に負担がかかることもあります。
必ずフードのラベルを見て、適量を守ることが大切です。
不安なときは、かかりつけの獣医さんに相談すると安心です。
グレインフリーや低アレルゲンは有効?
マラセチア皮膚炎やアレルギーなど、皮膚のトラブルが続くと、「フードが合ってないのかな?」と感じること、ありますよね。
最近よく見かけるのが「グレインフリー」や「低アレルゲン」と書かれたドッグフード。
実際、これらのフードが効果的なケースも多いんです。
でも、「とにかくグレインフリーにすればOK」という話ではありません。
ちょっとした“選び方のコツ”と“注意点”を知っておくと安心です。
グレインフリーはなぜ注目される?
「グレインフリー」とは、穀物(小麦、米、とうもろこしなど)を使っていないフードのこと。
穀物は炭水化物が多く含まれていて、マラセチア菌が増える“えさ”になりやすいと言われています。
また、小麦やとうもろこしにアレルギー反応を示す犬も少なくないため、皮膚が赤くなったり、かゆがったりする子には、グレインフリーが向いている場合があります。
低アレルゲンフードって?
「低アレルゲン」は、アレルギーの原因になりにくい原材料を使ったフードのことです。
例えば──
・タンパク源に、鶏肉ではなく魚や鹿肉を使っていたり
・添加物や着色料をできるだけ省いていたり
・原材料の数を絞って、シンプルにしていたりします
アレルギーの原因になりやすい食材を避けることで、皮膚や耳の状態が落ち着くこともあるので、慢性的にトラブルがある子には試してみる価値があります。
ただし、注意したいことも
「グレインフリー=必ず安心」と思われがちですが、実はイモ類(じゃがいも、さつまいもなど)で炭水化物を補っている商品も多いんです。
これらも糖質が高く、マラセチアが増える原因になることがあります。
また、低アレルゲンフードも、すべての犬に合うとは限りません。
「アレルギーを起こしにくい食材」でも、その子にとっては反応が出てしまうこともあるんです。
どう選べばいいの?
まずは今のフードの原材料を見て、穀物や甘味料が多く入っていないかチェックしてみましょう。
そして、「皮膚の赤み」「かゆみ」「耳のベタつき」などが気になるなら、試しにグレインフリーや低アレルゲンのフードに切り替えてみるのも一つの手です。
ただし、急に変えるのではなく、少しずつ混ぜて慣らすのがポイント。
変えてみて調子が良くなったかどうかは、便の状態や皮膚の様子を観察して判断しましょう。
添加物や保存料にも気をつけたい
ドッグフードを選ぶとき、つい「肉の種類」や「グレインフリーかどうか」ばかりに目がいきがちですが、見落としがちなのが“添加物や保存料”です。
でも実はここ、とても大事なポイントなんです。
そもそも「添加物」ってなに?
ざっくり言うと、「風味を良くしたり、長持ちさせたりするために後から加えられるもの」です。
たとえば──
・着色料(色をつけて美味しそうに見せる)
・香料(においを強くして食いつきを良くする)
・酸化防止剤(油の酸化を防ぐ)
・保存料(カビや菌の繁殖を防ぐ)
こういったものが入っていると、フードの見た目や香りは良くなるけれど、犬の体に負担がかかることもあるんです。
なぜ気をつけるべきなの?
人間と同じで、犬も毎日食べるものから体が作られます。
だからこそ、余計なものを少しずつでも摂り続けると、内臓や皮膚に負担が出ることもあるんですね。
特に皮膚トラブルがある子や、マラセチア皮膚炎のように菌のバランスが崩れやすい子は、添加物によって炎症が悪化することも。
保存料や香料などに反応して、かゆみや赤みが出るケースもあります。
「無添加=安心」ではないけれど…
最近は「無添加」と書かれたフードも増えてきましたが、注意したいのは「無添加=すべてが安全」というわけではないこと。
たとえば──
・無添加でも保存方法が悪いとすぐに傷む
・別の原材料で品質を補っているだけのケースもある
とはいえ、不要な添加物を避けることは、やっぱり皮膚や体調を整えるうえでプラスになります。
どうやって見分ける?
ちょっと面倒に感じるかもしれませんが、パッケージの裏面に書かれている「原材料表示」をチェックしてみましょう。
できれば避けたい添加物の一例:
・BHA(ブチルヒドロキシアニソール)
・BHT(ブチルヒドロキシトルエン)
・ソルビン酸カリウム
・赤色○号、青色○号などの人工着色料
逆に、安心できる保存料の例としては、天然由来の「ローズマリー抽出物」や「ビタミンE(ミックストコフェロール)」などがあります。
こういったものが使われているフードは、保存の工夫をしながらも自然に近い形で作られていることが多いです。
ドッグフード選びで失敗しないためのチェックリスト
ドッグフード選びは、愛犬の健康を左右する大切なポイントです。でもパッケージの言葉だけでは、本当に良いものかどうかは分かりません。そこで、購入前にチェックしておきたいポイントを簡単にご紹介します。
「原材料表」のどこを見るべきか
ドッグフードを選ぶとき、パッケージの見た目や「○○配合」「グレインフリー」などのキャッチコピーに目がいきがちですが、本当に見るべきは裏面にある「原材料表」です。ここを見れば、そのフードが何からできていて、どんな特徴があるかがある程度わかります。
まず注目したいのが原材料の一番最初に何が書かれているか。これは、そのフードの中で最も多く含まれている成分を示しています。たとえば「チキン」や「ラム肉」など、動物性タンパク質が最初に来ているかどうかは、良質なフードかを判断する一つのポイントになります。
次に気をつけたいのが、あまり聞き慣れない添加物や、曖昧な表現が多くないか。たとえば「○○ミール」や「動物性油脂」「副産物」などが続くようであれば、具体的に何が使われているのか不透明で、品質にばらつきがある可能性があります。
また、「小麦」「とうもろこし」「大豆」などの穀物類が多く使われているかもチェックポイント。これらは犬にとって消化しづらかったり、アレルゲンになることもあるので、皮膚トラブルが気になる子には避けたい成分です。
さらに、「合成保存料」「着色料」「香料」などが入っていないかも確認しましょう。犬にとって必要のない添加物は、長期的には健康に影響を及ぼすこともあります。
要するに、原材料表はそのフードの「中身」を知るための大事なヒント。よくわからないカタカナや、抽象的な表現ばかりのフードは避けて、できるだけシンプルで、何が入っているかひと目でわかるものを選ぶようにしましょう。
給与後の体調変化に注目する
給与(給餌)後の体調変化に注目する、というのは、ドッグフードが愛犬の体に合っているかどうかを見極めるために、とても大事な視点です。以下に、飼い主さんがチェックすべきポイントを、できるだけわかりやすくまとめます。
食べたあとの様子をよく観察しよう
ドッグフードを変えたあとや、新しいごはんを与え始めた時は、その後の体調に注目してみてください。「ちゃんと食べてるから大丈夫」と思いがちですが、食べる=合っているとは限りません。
よくあるサイン
以下のような変化があったら、食事が合っていない可能性があります。
・うんちの状態がいつもと違う
ゆるくなったり、逆にコロコロしすぎたりしたら注意。未消化のフードが混ざっていることも。
・おならや便のにおいが強くなる
消化に負担がかかっていたり、腸内環境が乱れているサインかもしれません。
・皮膚や毛に変化が出る
フケが増えたり、毛づやが悪くなったり、かゆがる様子がある場合は、アレルギーや栄養バランスの影響が考えられます。
・口臭が強くなる
原因は歯だけではありません。体内の消化の問題が口臭につながることもあります。
・元気がない・寝てばかりいる
食後にいつもぐったりしているようなら、エネルギーの吸収がうまくいっていない可能性も。
小さな変化も見逃さないことが大事
犬は不調を言葉で伝えられません。だからこそ、飼い主さんが「いつもと違うな?」と感じる小さな変化に気づいてあげることが大切です。
ドッグフードを変えたら、少なくとも2週間ほどは体調をよく観察しましょう。もし不安なことがあれば、遠慮せずに獣医さんに相談するのがおすすめです。
切り替えは慎重に少しずつ
ドッグフードを変えるときは、「パッと全部変える」のはちょっと待ってください。実は、フードの切り替えはとてもデリケートな作業で、愛犬の体に負担をかけないためには少しずつ慎重に進めることが大切です。
急な切り替えがNGな理由
人間でも、いきなり食生活がガラッと変わるとお腹を壊すことがありますよね?犬も同じです。とくに消化器官は敏感なので、突然まったく別のフードを与えると、
・下痢や軟便になる
・食欲が落ちる
・嘔吐する
といった体調不良が起こることがあります。
切り替えの目安:7日間くらいかけてゆっくりと
安全な切り替え方の基本は、「今までのフードに少しずつ新しいフードを混ぜていく」ことです。
以下のようなスケジュールで進めるのが一般的です:
| 日数 | 今までのフード | 新しいフード |
|---|---|---|
| 1〜2日目 | 75% | 25% |
| 3〜4日目 | 50% | 50% |
| 5〜6日目 | 25% | 75% |
| 7日目以降 | 0% | 100% |
※お腹が弱い子やシニア犬の場合は、10日〜2週間くらいかけてもOKです。
体調チェックを忘れずに
切り替え中は、うんちの状態・食いつき・元気さなどをこまめに確認してください。もし途中で体調を崩した場合は、切り替えのスピードを落とすか、いったん元のフードに戻すのが無難です。
焦らず、愛犬のペースに合わせて
「いいフードに変えたい」という思いがあるほど、急ぎたくなってしまうかもしれません。でも、焦らずゆっくりが愛犬のため。じっくり少しずつ慣らしていくことで、安心して新しい食生活に移行できますよ。
食事以外にもできるマラセチア対策
マラセチア対策は食事だけでは不十分。毎日の生活の中でできるケアも組み合わせることで、症状の悪化を防ぎやすくなります。
シャンプーや清潔な環境も大切
マラセチアの対策というと「食事」ばかりに目が行きがちですが、実はそれだけでは不十分です。皮膚の状態を良く保つには、日々のケアもとても重要です。
まず大切なのがシャンプーによる皮膚の清潔管理。マラセチアは湿度や皮脂の多い場所を好んで増殖するため、脂っぽくなった皮膚や毛にそのまま菌が残ってしまうと、悪化の原因になります。かといって洗いすぎるのも逆効果なので、獣医さんと相談しながら、その子に合った専用シャンプーを使って定期的にケアしてあげると良いでしょう。人間用のシャンプーや刺激の強いものは避け、犬用で低刺激かつ抗真菌作用のあるものがおすすめです。
次に意識したいのが、清潔な生活環境。寝床やマット、ぬいぐるみ、洋服など、皮膚に直接触れるものは雑菌が繁殖しやすいため、こまめな洗濯と乾燥が必要です。特にジメジメした季節は注意が必要で、室内の除湿や通気性の確保も、菌の増殖を防ぐうえで効果があります。
また、耳や指の間、しっぽの付け根など蒸れやすい部分のケアも忘れずに。マラセチアが出やすい「特定の場所」は犬によって異なるため、普段のブラッシングやスキンシップの中で、「あれ、ちょっと赤い?」「ニオイが気になるかも」などの変化に気づいてあげられるとベストです。
毎日の少しの手間で、愛犬の皮膚トラブルはぐっと減らせます。食事と並行して、こうしたお手入れも意識していきましょう。
皮膚の状態に合わせたケア
マラセチアの症状は、犬によって出方がさまざまです。かゆみが強くて赤くなっている子もいれば、ベタつきやフケ、脱毛が目立つ子もいます。そのため、皮膚の状態に合ったケアをしてあげることが大切です。
たとえば、赤みや炎症が強いときは、刺激の少ない低刺激のシャンプーや薬用シャンプーを使って、やさしく洗ってあげるのが基本。逆に乾燥がひどい場合は、保湿成分が入ったスキンケア用品を使って潤いを保つケアが必要になります。
また、症状が落ち着いてきたら、週に1〜2回のシャンプーで清潔を保つ「予防ケア」も効果的です。皮膚の状態は季節や体調によって変化しやすいので、定期的に観察しながら、今の状態に合った方法を選んでいくことが、マラセチアと上手に付き合っていくコツです。
動物病院での相談のすすめ
マラセチア皮膚炎は、見た目やにおいでなんとなく気づけることもありますが、自己判断だけでの対処には注意が必要です。というのも、似たような症状を起こす別の皮膚病もたくさんあるからです。かゆみや赤みの原因が実は別の菌だったり、アレルギーだったりすることも少なくありません。
だからこそ、一度は必ず動物病院で診てもらうのがおすすめです。マラセチアかどうかを顕微鏡などで調べてもらえば、原因がはっきりしますし、その子の症状や体質に合わせて、適切な薬やシャンプーの指導をしてもらえます。
また、ドッグフードの選び方や生活環境についてのアドバイスもしてくれる場合があります。ネットや口コミだけでは得られない、「その子専用」の対策が見つかることも多いので、遠慮せず相談してみましょう。早めに専門家の手を借りることで、つらい症状が長引かずに済むこともあります。
まとめ
マラセチア皮膚炎に悩む愛犬には、食事の見直しが大きな助けになります。余計な添加物を避け、オメガ3脂肪酸などの皮膚サポート成分がしっかり含まれたフードを選ぶことが大切です。また、アレルゲンになりにくい原材料を選び、少しずつ慎重に切り替えていくことも忘れずに。毎日のごはんが、愛犬の肌の健康を支える力になります。

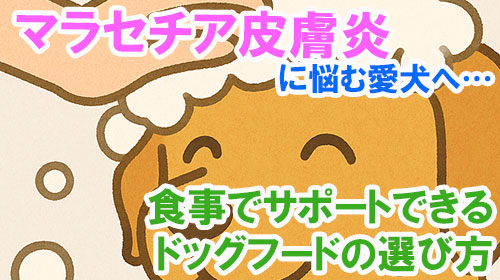
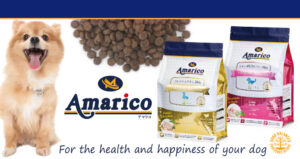
』の口コミ・わんちゃんの写真-120x68.jpg)

コメント